医療的ケア児を育てていらっしゃるお母さん、お父さん。 毎日、お子さんのケアと向き合い、本当に本当にお疲れ様です。 時に、深い孤独を感じることはありませんか? 「周りに理解してくれる人がいない」「誰にも相談できない」「一人で全てを背負っている」――そんな感情に押しつぶされそうになることもあるかもしれません。
私自身、30年以上現場で看護師として多くの医療的ケア児とそのご家族を見てきました。その中で、多くの親御さんが「孤独」と必死に闘っている姿を間近で感じてきました。
この記事では、そんな医療的ケア児のご家族が感じやすい「孤独」という感情にどう向き合い、乗り越えていくかについて、現場看護師としての視点と、実際に孤独を乗り越えた親御さんの声(イメージ)を元に、具体的なヒントと、安心して頼れる相談先をご紹介します。
あなたが一人ではないこと、そして希望を見つけるための道があることを、心からお伝えしたいと思います。
1. 医療的ケア児の親が「孤独」を感じやすい理由
なぜ、医療的ケア児の親は孤独を感じやすいのでしょうか。その背景には、いくつかの共通した要因があります。
- 周囲との生活様式の違い:
- 一般的な子育てとは異なる特別なケアが必要なため、周囲の親御さんとの共通の話題が少なく、疎外感を感じることがあります。
- 急な体調変化や通院などで、社会との接点が減りがちになります。
- 社会の理解不足:
- 医療的ケアの知識がない人からは「大変そう」と安易に言われたり、好奇の目で見られたりすることもあり、心が傷つくことがあります。
- 偏見や誤解から、外出をためらったり、人との交流を避けたりすることも。
- 物理的・時間的制約:
- 24時間体制のケアが必要な場合もあり、自分の時間や休息がほとんど取れないことがあります。
- 自由に外出することが難しく、社会的に孤立してしまうケースも少なくありません。
- 情報不足と手探りの状態:
- 必要な情報がなかなか手に入らず、常に手探りでケアや制度利用を進めなければならないという心理的負担があります。
- 身近な人とのズレ:
- 時には、夫(妻)や親しい友人、親族でさえも、ケアの重さや心の負担を完全に理解しきれないことがあります。
これらの要因が重なり、知らず知らずのうちに深い孤独感に陥ってしまうことがあるのです。
2. 『孤独』と向き合うための具体的なヒント
孤独を感じた時に、少しでも心が軽くなるような、具体的なヒントをご紹介します。
(1) まずは「孤独を感じている自分」を認める
- 「私だけがこんなに苦しい」と感じるのは、決してあなただけではありません。多くの医療的ケア児の親が同じような感情を抱えています。
- 「孤独を感じてはいけない」と蓋をするのではなく、「今、私は孤独を感じているんだな」と、その感情を否定せずに受け入れてあげることが第一歩です。自分を責める必要は全くありません。
(2) 完璧を目指さない「割り切る勇気」を持つ
- 医療的ケアと子育てを両立させる中で、全てを完璧にこなすことは不可能です。家事や仕事、自分の趣味など、どこかで「割り切る勇気」を持つことも大切です。
- 「今日はこれだけできたからOK」と、自分を褒めてあげる習慣をつけましょう。
(3) 物理的・精神的な「隙間時間」を意識的に作る
- たとえ10分でも、お子さんから離れて自分のためだけの時間を作ることを意識してください。
- 身体を休める: 少し横になる、深呼吸をする。
- 好きなこと: 温かい飲み物を飲む、好きな音楽を聴く、数ページだけ本を読む、短い動画を見る。
- 訪問看護や一時預かりサービスなど、使える制度は積極的に活用し、物理的な休息時間を確保しましょう。
(4) 感情を「書き出す」または「声に出す」
- 誰にも言えない感情は、ノートに書き出したり、スマホのメモ機能に入力したりするだけでも、心が整理されることがあります。
- 信頼できる(と感じる)医療者や相談支援専門員に、正直な気持ちを話してみるのも良いでしょう。
(5) 自分の「頑張り」を認めて褒める
- 毎日、お子さんの命を守り、成長を支えているあなたは、本当に素晴らしい存在です。
- 「誰かが褒めてくれる」のを待つのではなく、「今日も私、よく頑張った!」と、自分で自分をねぎらい、褒めてあげましょう。
3. 「孤独」を乗り越えるための具体的な「繋がり」のヒント
孤独を乗り越えるには、新しい「繋がり」を見つけることが非常に有効です。
(1) 同じ境遇の親との交流(ピアサポート)
- オンラインコミュニティ: SNSやブログ、特定のウェブサイトで医療的ケア児の親が集まるオンラインコミュニティに参加してみましょう。顔が見えなくても、共感できる仲間がいるだけで大きな支えになります。
- 地域の交流会・サロン: 自治体やNPOが主催する医療的ケア児の親の会、交流会に参加してみましょう。実際に顔を合わせて話すことで、より深い繋がりが生まれることがあります。
- 「あ、うちも同じ!」という共感は、孤独感を和らげる最大の薬です。
- 縦横の繋がり: 同じ年齢のお子さんを持つ親御さん(横の繋がり)だけでなく、少し成長したお子さんを持つ先輩ママさん・パパさん(縦の繋がり)から、経験談や具体的なアドバイスを聞ける機会は、今後の見通しを持つ上でも大きなヒントになります。
(2) 児童発達支援・放課後等デイサービスの活用
- お子さんが一定の年齢に達し、利用できる状態であれば、児童発達支援(未就学児)や放課後等デイサービス(小学生〜高校生)の利用を検討しましょう。
- これらの施設は、お子さんの発達支援を行うだけでなく、ご家族が日中の時間を確保し、休息を取るための貴重な機会となります。
- 中には、重症心身障害児を専門とする施設もあり、医療的ケアにも対応できる看護師が常駐している場所もあります。
- 私の職場でも2歳半ごろからのお子さんを受け入れており、保護者の方々が安心して利用されています。
- 実際、お母さんの精神的な負担が大きい場合は、2歳3ヶ月といった早い段階から利用を始めたケースもありました。 孤独と戦いながら懸命にお子さんを支え、その経験から後に看護師になったお母さんもいらっしゃるほどです。これらのサービスが、どれだけご家族の支えになるかを示す一例です。
- 利用には、市町村への申請(受給者証の取得)が必要ですので、お住まいの地域の障害福祉課や相談支援事業所に相談してみましょう。
(3) 地域の専門機関・相談支援事業所を活用する
- 市町村の福祉担当窓口: 障害福祉課や児童福祉課など。利用できる制度やサービスについて、一歩踏み込んで相談してみましょう。
- 相談支援事業所: 相談支援専門員が、個々のお子さんとご家族のニーズに合わせたサービス利用計画(ケアプラン)の作成や、関係機関との調整を行ってくれます。利用できるサービスを網羅的に教えてくれる心強い存在です。
- 地域の保健センター(保健師): 定期的な訪問や相談を通じて、ご家族の状況を理解し、様々な支援の入り口となってくれます。
- 訪問看護ステーション: 実際に自宅に来てケアをしてくれる看護師は、お子さんの状態だけでなく、ご家族の状況もよく理解してくれます。日々の悩みや不安を打ち明けられる、最も身近な専門家です。
(4) 病院内の専門家を頼る
- 退院調整看護師/医療連携室/医療相談室: お子さんが入院中の場合、退院後の生活や在宅サービスについて、具体的な相談に乗ってくれます。孤独を感じる前に、早い段階から繋がりを持つことが大切です。
- 主治医: 体調やケアに関する悩みだけでなく、精神的な負担についても正直に話してみましょう。必要に応じて専門医やカウンセリングを紹介してくれることもあります。
(5) 地域の支援者・ボランティアとの連携
- 地域のNPO法人やボランティア団体が、医療的ケア児とその家族をサポートする活動を行っていることがあります。情報がないか、地域の社会福祉協議会などに問い合わせてみましょう。
まとめ:あなたは一人じゃない。頼れる場所は必ずある
医療的ケア児を育てる上で感じる「孤独」は、誰しもが抱えやすい自然な感情です。 大切なのは、その感情を一人で抱え込まず、外へ向かって声を上げること、そして頼れる場所や仲間を見つけることです。
あなたが抱える感情は、決して特別なものではありません。そして、あなたの頑張りを理解し、支えたいと願う専門家や、同じ経験を持つ仲間が必ずいます。
小さな一歩からでも構いません。今日ご紹介したヒントを参考に、どうか孤独を乗り越えるための「繋がり」を見つけてください。
関連リンク

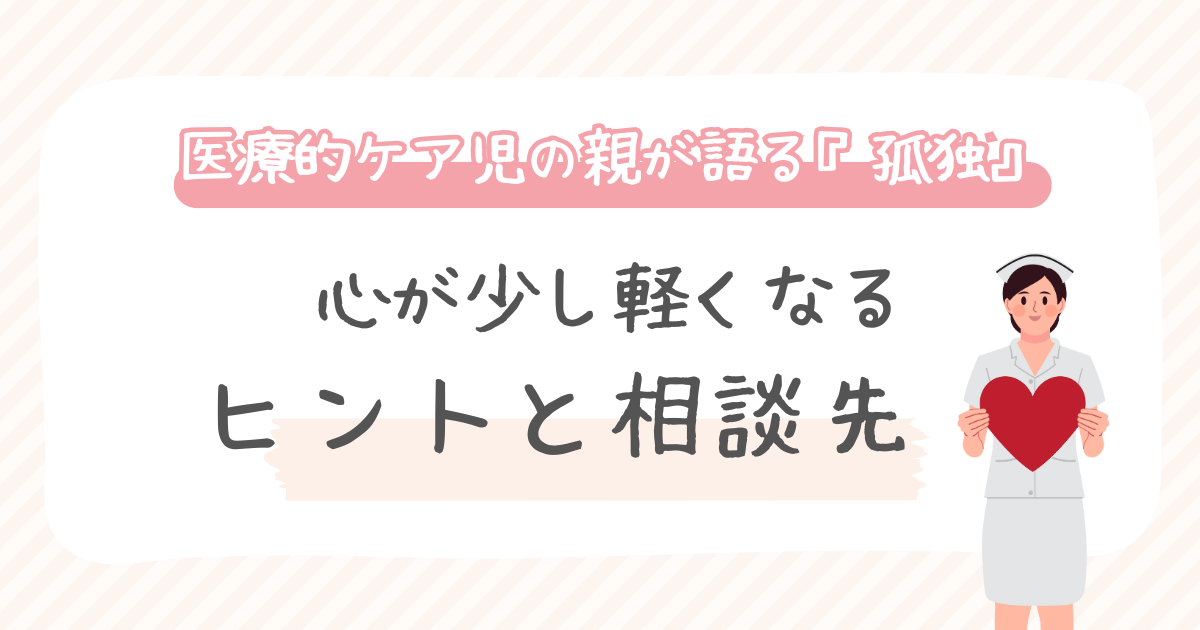

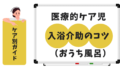
コメント