「医療的ケアって、具体的には何を指すんですか?」
この質問、実は看護師でも答えに迷うことがあります。 ましてや、保育士さんや教員、介護士、そしてご家族にとっては、なんとなく“特別なケア”というイメージはあっても、どこまでが医療的ケアで、誰がやっていいのかが、よくわからないというのが本音ではないでしょうか。 私自身、看護師として30年の経験があったとて、「この説明を簡潔に、かつ正確に伝えるのは難しいな…」と感じることがあります。
この記事では、厚生労働省や文部科学省のガイドラインをベースにしながら、「医療的ケアって結局なに?」という問いを、初心者にもわかりやすく、現場感覚も交えて解説します。
対象は、ご家族、支援者、教育・保育・福祉・医療関係者すべて。 知らなくて当たり前、「なるほど」と思えるはじめの一歩になれば嬉しいです。
医療的ケアの定義|そもそも「医療」なの?「介護」なの?
医療的ケアとは、厚生労働省によると――
「喀痰吸引や経管栄養等、医師の指示に基づき実施される医療行為のうち、日常的に行われるもの」 と定義されています(出典:喀痰吸引等研修ガイドライン)。
つまり、
- 医師の指示が必要な「医行為」である一方で
- 病院だけでなく、家庭・学校・福祉施設など生活の場でも行われ
- その人の日常生活の一部になっているケア
…と位置づけられています。
これらはかつて、医師や看護師等にしか許されていなかった行為でしたが、法改正と研修制度の整備により、一定の条件を満たせば、非医療職も実施可能になったという経緯があります。
具体的なケアの例
代表的な医療的ケアには、次のようなものがあります。
- 喀痰吸引(口腔・鼻腔・気管カニューレ)
- 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻栄養)
- 酸素吸入・人工呼吸器の管理
- 導尿 など
医療的ケアを必要とするのは「子ども」だけじゃない
「医療的ケア児」という言葉がメディアでも取り上げられ、認知が広がってきました。 しかし、医療的ケアを必要とするのは子どもだけではありません。
- 高齢者施設で胃ろうや吸引が必要な方
- 難病や神経疾患を抱える成人
- 重度障害者の方が成人期を迎えているケース
など、医療的ケアを必要とする人は全年齢にわたって存在しています。
これは、医療的ケアを必要とする人が全年齢にわたっているにもかかわらず、日本の制度が対象者別に縦割りになっている現状を示しています。この縦割り構造が、現場で働く支援者が年齢層をまたがって対応する難しさや、一貫した情報共有の障壁となっています。
だからこそ、「医療的ケアって何?」という全体像を知ることが、支援に関わるすべての人にとって必要なことなのです。
「誰がやるのか」問題|教員・保育士・介護士・看護師の分担と誤解
「このケア、だれがやるの?」「自分がやっていいの?」という不安は、医療・福祉・教育の現場で毎日のように出てくるテーマです。
1号・2号・3号研修とは?
看護師以外の職種が医療的ケアを行うためには、「喀痰吸引等研修」の修了が必要です。 この研修は、2012年4月1日に施行された社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律に基づき、それまで医師や看護師にしか認められていなかった喀痰吸引や経管栄養等の医療行為について、一定の研修を修了した介護職員等が、医師の指示と連携のもとに行うことができるようになりました。
この研修には、ケアの対象や手順に応じて、以下の3つの研修があります。
| 種類 | 正式名称 | 実施できる範囲 | 主な対象職種 |
| 1号研修 | 特定行為業務従事者研修(不特定の者に対する喀痰吸引等) | 不特定多数の利用者に共通手順で対応(主に施設で複数の利用者に対応) | 介護士、保育士など |
| 2号研修 | 特定行為業務従事者研修(特定の者に対する喀痰吸引等) | 特定の利用者に対し、個別手順に基づいて実施(利用者ごとの個別対応) | 介護士、保育士など |
| 3号研修 | 特別支援学校の教員等が行う喀痰吸引等研修 | 学校で特定の児童生徒に対して実施(学校用カリキュラム) | 教員、養護教諭など |
補足:
- 3号研修の実施主体は都道府県知事であり、都道府県教育委員会がとりまとめ、実際の研修は指定の研修機関(訪問看護ステーション等)に委託されることが一般的です。
- 1号研修と2号研修は正式名称が同じですが、実施できる範囲(不特定多数 vs 特定の個別対象)に明確な違いがあります。
- ※各研修の詳細は別の記事で解説します。
「研修を受けた=できる」ではない
研修修了は第一歩ですが、実際の医療的ケアを実施するためには、以下の要素が必須です。
- 医師の指示書があること
- ご家族の同意があること
- 適切な管理体制が整っていること
施設長や学校長などの管理者が、安全な体制を整え、緊急時の対応マニュアルや記録方法も含めて責任を持つ必要があります。 つまり、「研修を受けたから自動的にできる」わけではないということを、実施者も、組織全体も、しっかり理解しておく必要があります。
看護師がいない時間はどうする?
例えば、現場では次のような状況が起こることがあります。
- 看護師が送迎に同行している間、施設内での吸引が必要になる
- 学校で下校時間帯だけ看護師が不在になる
- 看護師の休憩中に、発作やトラブルが起こる
このようなときに、やむを得ず教員や介護士、保育士がケアを行う場合があります。 しかし、そのような状況下では、「その時間帯の責任体制が曖昧」なことも多く、“暗黙の了解”で現場が回っている状態になりがちです。
医療的ケアのこれから|共に生きる社会を支える“共通知識”として
医療的ケアは、もはや専門職だけのものではありません。 共生社会、地域包括ケア、家庭支援―― 今後は「支える人すべて」が最低限知っておくべき共通知識になります。
「知らないことで怖くなるのは当たり前。」
でも、知ればきっと、不安より安心が増えていくはずです。
まとめ|“知らない”から“知ってみよう”へ
医療的ケアは、“専門的で特別なこと”に見えるかもしれませんが、本質は、**その人が暮らしていくための“日常のケア”**です。
家族のため、子どものため、利用者のため―― 私たちは少しずつ、知って、つながって、支え合っていくことができます。
「知らない」から「知ってみよう」へ。
その一歩を踏み出したあなたは、きっと誰かの支えになれる人です。
関連リンク

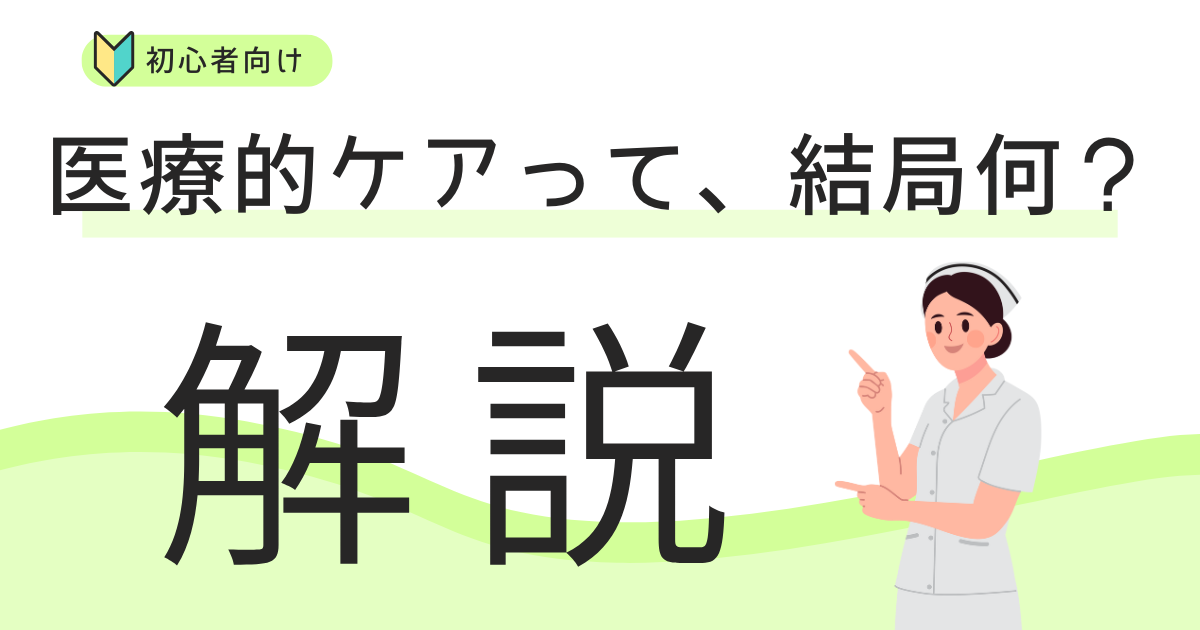
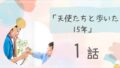

コメント