「それ、医療行為だからできません」と言われたことありませんか?
医療?介護?いったいどっち?
「これって、医療?介護?どっちの仕事なの?」
福祉や教育、在宅の現場で働いていると、必ずぶつかるこの疑問。ときには、やってあげたい気持ちがあっても、「それは医療行為なのでできません」と断られ、モヤモヤした経験がある人も多いのではないでしょうか。
実はこの“境界線”――想像以上に、あいまいでグレーなんです。
この記事では、看護師として30年の現場経験がある筆者の視点から、「医療」と「介護」の違いについて、法律や制度の背景も交えながら、できるだけやさしく、具体的に解説します。
医療行為と介護行為|法的にはどう違う?
まず、ざっくりとしたイメージで言うと:
- 医療行為=医師の判断・指示のもとに、医師や看護師だけができる行為
- 介護行為=日常生活を支えるためのケア(食事介助、排泄支援など)で、介護職や家族でもできる行為
では、法律上はどうなっているのでしょうか?
■ 医療行為とは
「医行為(いこうい)」とも呼ばれ、医師法第17条により、原則として医師以外の者が行ってはならないとされています。ただし、看護師は**保健師助産師看護師法(保助看法)**により、医師の指示のもとで医療行為を行うことができます(このとき、診療の補助としての業務に該当します)。
■ 介護行為とは
医療行為には当たらず、生活を支援するための身体介助など、主に介護福祉士などの専門職や、家族が行うことが想定されるケアです。法的に医師や看護師のような独占業務とはされていませんが、適切な研修や指導のもとで行うことが重要です。
グレーゾーンが多い理由|なぜ境界があいまいなのか?
実際の現場では、医療と介護が完全に分かれているわけではありません。たとえば:
- 体位変換やおむつ交換中に、褥瘡の処置が必要になった
- 食事介助中に、むせ込み対応として吸引が必要になった
こういった場面では、「これは医療?」「介護職がやっても大丈夫?」と迷うことが出てきます。
■ なぜこんなにあいまい?
- 法整備が現場のニーズに後追いだったため(新しいケアのニーズが現場で生まれ、後から法整備が追いついた)
- 対象者の状態によってケアの“医療的リスク”が変わるため
- 医療的ケアが“生活の一部”になっている
たとえば、胃ろうからの栄養注入や喀痰吸引は、かつては医師や看護師しか行えない「医療行為」でした。しかし、平成24年(2012年)の社会福祉士及び介護福祉士法等の改正により、一定の研修を修了し、医師の指示のもとで行えば、介護職員等(介護士や教員など)も実施できるようになりました。
「できる」と「やっていい」は別問題|責任の所在を明確に
現場では、「研修を受けたから大丈夫」「自宅では家族がやってるから…」という声も聞かれます。しかし、ここで最も大切なのは、「そのケアを、誰が、どのような責任のもとで実施しているのか?」という視点です。
■ 医療行為を“していい人”は限られている
たとえば:
- 看護師:医師の指示があればOK
- 介護士:喀痰吸引等研修を修了+医師の指示書+所属施設の管理体制があればOK
- 教員や保育士:3号研修等を受講+医師の指示+校長や園長の責任体制が必要
つまり、「研修を受けた=どこでも自由にできる」ではありません。
■ 責任の所在は?
- 指示を出す医師:医療的ケアの実施には、必ず医師の指示書が必要です。医師が最終的な責任を負います。
- 管理者(施設長、学校長、事業所責任者など):実施体制を整備し、安全管理に責任を持ちます。
- 実施者(看護師、研修修了者):医師の指示と管理者のもとで、安全・適切にケアを行う責任があります。
(補足:医療的ケア児支援法では、関係機関の連携体制も重視されています)
このトライアングルがきちんと機能していないと、いざというときにトラブルになります。
境界線ではなく“連携線”へ
医療と介護の境界線を正しく知ることはとても大切です。
でも、それは「やれること/やれないこと」を線引きするためだけではありません。
- どう連携するか?
- どこでバトンタッチするか?
- 何を共有すべきか?
そうした視点を持つことで、支援の質がぐっと上がります。
まとめ|「自分にできること」を知ることは、チームの強さにつながる
医療と介護の違いを知ることは、“自分の限界を知る”ことではありません。
それはむしろ、「自分にできること」と「仲間に託すこと」の境界を明確にし、支援チームとしての信頼を築くための一歩です。
あなたのその迷いは、誰かを大切にしたいと思う気持ちから生まれたもの。だからこそ、知って、つながって、安心して支える。そんな現場が増えますように。

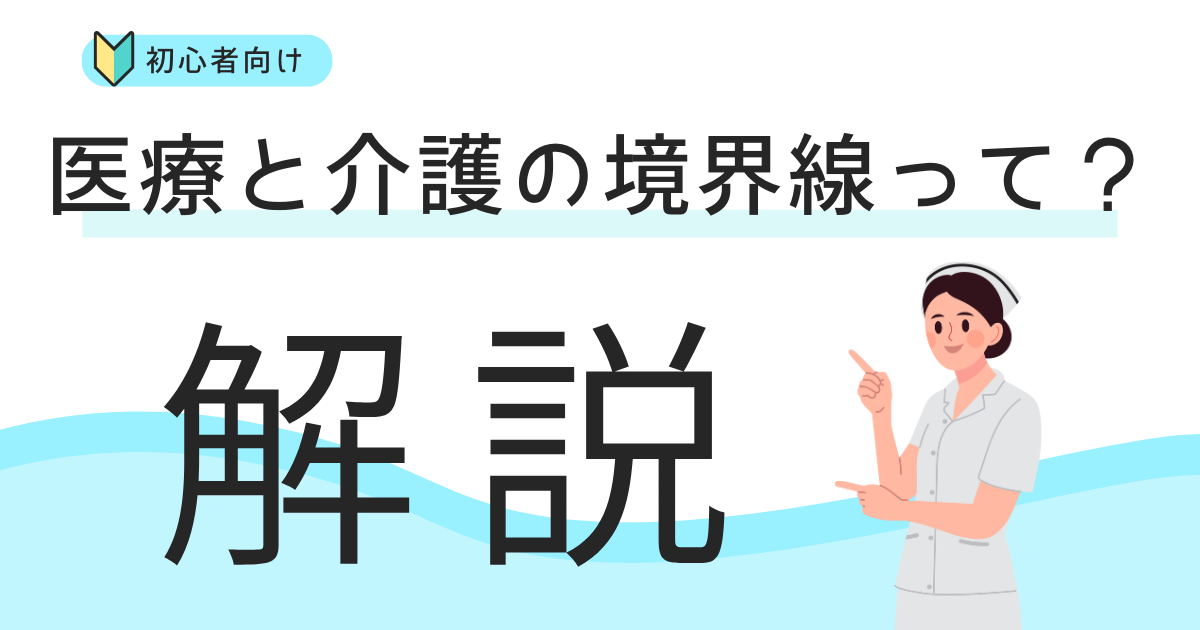
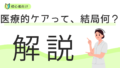
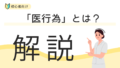
コメント