実は看護師も誤解してる落とし穴|基本ルールを徹底解説
「『医行為』って、実際どこまでのことを指すの?」
そんな疑問を抱えたことはありませんか?
特に、介護職や保育士、支援者として現場に関わっている方にとっては、「これって医行為なの?やっていいのかな?」と迷うシーンが後を絶ちません。
この記事では、そのモヤモヤを解消すべく、法律的な定義に加えて、現場で起きがちな誤解ポイントをやさしく解説します。
介護職、看護師、保育士、支援者の方に向けて、「やってもいいライン」と「ダメなライン」を明確にしていきますね。
医行為ってなに?法律ではどう定義されているの?
医行為の定義の根拠は「医師法」と「厚生労働省通知」
「医行為」は、医師法第17条に根拠があります。
「医師でなければ、医業をしてはならない」(医師法第17条)
ただし、この「医業」という言葉が法律上、具体的に定義されていないため、実際の判断には厚生労働省の通知や過去の判例が使われています。
医行為の代表的な例
代表的な「医行為」としては、次のようなものがあります。
- 診察、診断(例:打診・触診)
- 注射・点滴・採血
- 処方の判断
- 気管内吸引、経管栄養(これらは本来医行為ですが、一定の研修を修了した者のみ、医師の指示のもとで実施可能です)
- 手術や麻酔の管理 など
「人体への危害のリスク」が判断基準
厚生労働省の通知(昭和23年医発第505号)では、「医行為」を次のように定義しています。
「医師の判断と責任のもとでしか行えず、人体に危害を及ぼすおそれのある行為」
この「危害の可能性」があるかどうかが、医行為かどうかを見分ける重要なポイントになります。
よくある誤解①
「看護師がやってる=医行為ではない」?
これはよくある誤解です。
たしかに、看護師が日常的に行っている処置の中には、医行為が含まれていることがあります。
しかし、それは医師の指示のもと、看護師が「診療の補助」として医行為を代行できる場合があるというだけのこと。
「看護師ができる=それは医行為ではない」というのは誤りです。
よくある誤解②
「介護職や教員が医行為をしても大丈夫」?
これも非常に危険な誤解です。
基本的に、介護職や支援職、教員などが医行為を行うのは原則として認められていません。
しかし、この「原則」には例外があります。平成24年の制度改正により、一定の条件下で「喀痰吸引」や「経管栄養」などの一部の医行為に限り、非医療職でも実施が認められる制度が整備されました。
その条件とは:
- 医師の指示書があること
- 指定の研修を修了していること(喀痰吸引等研修)
- 適切な管理体制があること
ただし、それ以外の医行為を「ついやってしまう」「頼まれて…」というケースは、違法行為になるリスクがあります。
「診療の補助」ってなに?看護師と医行為の関係
これは、保健師助産師看護師法(看護師法)第5条に定められているキーワードです。
「看護師は、医師、歯科医師の指示のもとに、療養上の世話または診療の補助を行う」
つまり、看護師は「医師の指示のもと」に限って、医行為の一部を実施することができるのです。
この「診療の補助」という言葉があるからこそ、医行為の一部が看護師に任されているのです。
医行為かどうか迷ったら?現場でできる対応
「医行為」と判断される典型的なケースとグレーゾーン
例えば次のような場面では、迷うことが多いです。
- 痰が絡んで苦しそう。吸引していい?
- 胃ろうのボタンが抜けた。挿し直していい?
- 経管チューブが詰まった。水で流していい?
- 発作で倒れた。薬を口に入れていい?
これらは、行為の内容・対象者の状態・事前の指示内容などによって、医行為と判断される場合もあれば、そうでない場合もあります。
医行為かどうかを判断するポイント
- 医師の判断が必要な内容か?
- 失敗すると重大な危険があるか?
- 研修修了者として許可されているか?
- 現場に医師・看護師はいるか?
- 実施マニュアルや同意書があるか?
迷ったときの対処法
- 「念のため確認してから」にする
- 上司や医療職にすぐ相談する
- マニュアルや同意書の内容を読み返す
- 状況をメモや報告書に残す
まとめ|医行為は「できるかどうか」ではなく「やっていいかどうか」
「医行為」とは、原則として医師しか行えない行為のこと。
ただし、看護師が医師の指示のもと「診療の補助」として行えるケースや、一定条件下で介護職が行える「特定の行為」もあります。
でも大切なのは、「できるから」ではなく、「法律的にやっていいかどうか」を常に意識すること。
不安や疑問を感じたら、すぐに確認して、安全で安心なケアを一緒に守っていきましょう。
関連リンク

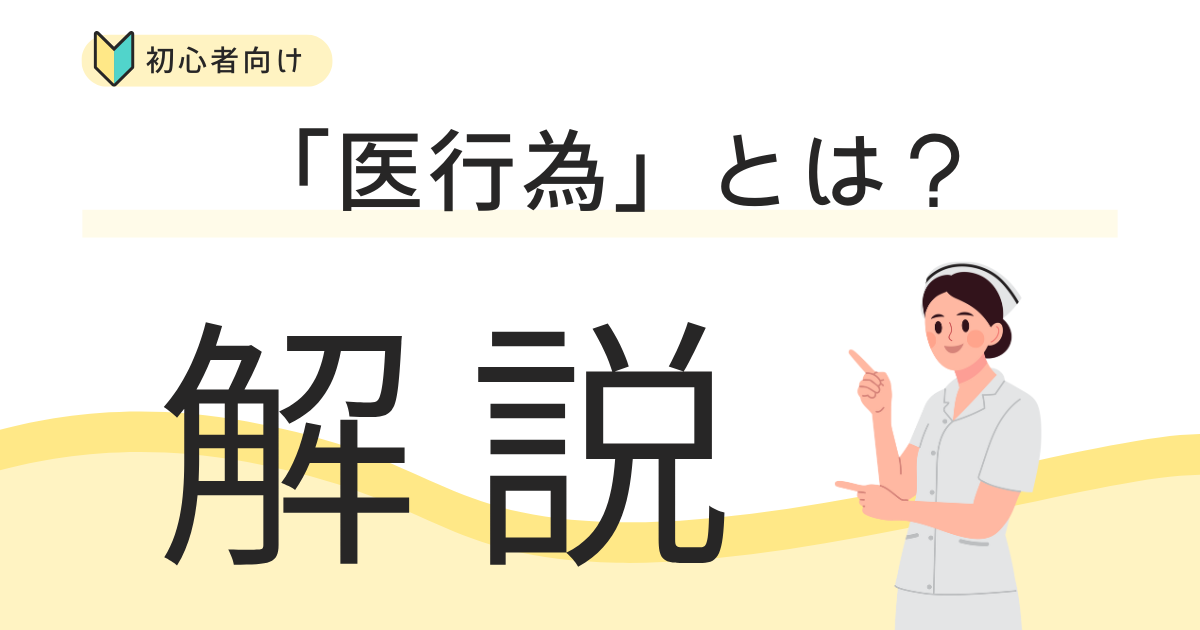


コメント