〜吸引の種類と現場リアルを、看護師歴30年がやさしく解説〜
喀痰吸引とは?まずは基本のキから
呼吸がしづらくなってしまう原因のひとつに、「痰(たん)」の詰まりがあります。
ときに窒息や誤嚥性肺炎に繋がる恐れがあり、命に関わるため、適切な吸引は呼吸ケアの要(かなめ)と言えます。
なぜ必要?吸引が必要な理由とは
吸引が必要なケースはさまざまです。
代表的なのは、神経や筋の病気で、自力での排痰が困難な場合や、嚥下(えんげ)・呼吸に障害があるケース。
また、意識障害や発達障害、乳幼児・高齢者で痰をうまく出せない場合などもあります。
吸引の目的は、
- 気道を確保すること
- 感染(肺炎)を予防すること
- 呼吸をラクにすること
などです。
吸引には種類がある|部位別3タイプ
① 口腔吸引(こうくう)
口の中に溜まった痰や唾液を吸い出します。
食事後や就寝前、話したあとなどに使われることが多いです。
- 吸引チューブは、舌の奥や咽頭部まで深く突っ込みすぎないように
- 歯のすき間、舌の裏などに残りやすい部分は丁寧に
👩⚕️「歯のすき間や舌の裏側に痰が残りやすいので、やさしく丁寧に」
② 鼻腔吸引(びくう)
鼻からチューブを挿入し、上咽頭から痰を吸引します。
違和感が強く、泣いたり嫌がることが多いケアです。
- やさしくゆっくりとチューブを入れ、強い痛みがあるときは中止
- 粘膜を傷つけないよう注意
👩⚕️「鼻の中はデリケートなので、無理せず、本人の反応をよく見ながら」
③ 気管カニューレ吸引(きかん)
人工呼吸器や気管切開をしている人に対し、気管内から直接痰を吸います。
感染予防や命に関わるケアのため、特に慎重な技術と観察力が必要です。
- 吸引チューブは、気管カニューレの長さを超えて奥に入れすぎない
(※粘膜を傷つけるリスクあり。抵抗があればそれ以上進めないこと)
「呼吸が浅くなったり、顔色が変わったらすぐに中止。緊張感が必要なケアです」
よくある誤解と現場のあるある
「吸引器があれば誰でもできる?」
→ ❌ いいえ、吸引は原則「医行為」です!
- 医師の指示が必要で、勝手に実施することはできません。
- 看護師以外が行うには、喀痰吸引等研修(1〜3号研修)の修了と、施設側の体制整備、医師の指示書などが必要です。
※研修制度や法的ルールについては【👉[「医行為とは?」の記事】で詳しく解説しています。
吸引の対象は子どもだけじゃない
吸引が必要なのは、重症心身障害児だけではありません。
- 高齢者施設
- 医療的ケアの必要な成人
- 脳血管障害後の方
- ALSなど神経疾患のある方
など、年齢に関係なく、必要な人が多くいます。
でも、吸引ケアは「誰がやるの?」「学校や施設での責任は?」など、現場の不安も大きいケアの一つです。
だからこそ、吸引というケアの意味や種類、安全な方法を知ることが、支援の第一歩。
まとめ|吸引は“命を守るケア”だからこそ、正しく理解を
吸引は、見た目よりずっと奥深く、命に関わるケアです。
誰かが当たり前のようにやっているように見えても、
その背景には知識・判断力・制度と責任体制が必要です。
「吸引ってそういうことだったのか」と思ってもらえたら嬉しいです。
そして、必要な人に必要な吸引が、安全に届けられる社会に。
関連リンク
📘 参考資料:
- 厚生労働省「喀痰吸引等の実施に関する手引き」
- 医療的ケア児支援法・関連ガイドライン
- 喀痰吸引等研修ガイドライン


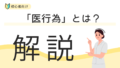

コメント