はじめに:なぜ「研修区分」が気になるの?
医療的ケアの現場でよく耳にする「1号研修」「2号研修」「3号研修」って、いったい何が違うの?と思ったことはありませんか? 訪問介護、特別養護老人ホーム、障害福祉施設、学校、グループホーム……どの現場でも、「医療的ケアを誰がどこまでやっていいのか」が話題になることが増えました。 特に、
- 介護職がたんの吸引をやってもいいの?
- 実務者研修を受けていれば何でもできる?
- 学校の先生が医療行為をするのは合法?
など、疑問は尽きません。 この記事では、そもそもの制度の全体像と、どうして現場とギャップが生まれやすいのかを、やさしく丁寧に解説します。
1号・2号・3号研修ってなに?制度の全体像を解説
スタートは「喀痰吸引等研修制度」
「喀痰吸引等研修」は、介護職員などがたんの吸引や経管栄養といった医療的ケアを行えるようにするため、平成24年(2012年)に始まった制度です。 法律上「医行為」とされていたこれらのケアは、本来は医師または看護師しかできないものでした。しかし、重度の障がいがある方や高齢者が住み慣れた地域や自宅で生活を続けるには、医療的ケアを日常的に提供できる体制が不可欠です。 そのため、安全を確保した上で、一定の研修を受けた介護職員などが、医師の指示と連携のもと、条件付きでケアを実施できるように整備されました。
【できるようになる主な医療的ケア】 この研修を修了することで、特定の条件下において以下の医療的ケアを実施できるようになります。
- 喀痰吸引: 口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部の吸引
- 経管栄養: 胃ろう、腸ろう、経鼻からの栄養剤注入
1号・2号・3号のちがいとは?
ひとくちに「喀痰吸引等研修」といっても、その対象者や実施範囲によって、以下の3つの区分に分かれています。
| 種類 | 実施できる範囲 | 主な対象者 |
| 1号研修 | 不特定多数の利用者に対し、共通の手順に基づいて医療的ケアを実施(主に施設などで複数の利用者に広く対応) | 介護職員、保育士など(幅広い施設での対応が想定される) |
| 2号研修 | 特定の利用者に対し、その利用者の個別の手順に基づいて医療的ケアを実施(利用者ごとの個別対応) | 介護職員、保育士、ヘルパーなど(個人宅や小規模施設) |
| 3号研修 | 特別支援学校の教員等が、学校で特定の児童生徒に対して医療的ケアを実施 | 教員、養護教諭、学校における支援員など |
それぞれの研修は、目的や実施現場、対象となる利用者の状況によって必要な知識・技術が少しずつ異なっています。
制度の背景にあるのは「人材不足」と「生活の質の向上」
この制度ができた背景には、「医療的ケアができる専門職(医師・看護師)が圧倒的に足りない」という現実と、「医療的ケアが必要な人が、病院だけでなく住み慣れた場所で安心して暮らしたい」というニーズの高まりがありました。 医療的ケアを、「専門職が限定的に行うもの」から「日常生活を支えるケアの一部」として位置づけることで、より多くの人が地域で安心して生活できるよう支援体制を強化することが目的です。
実務者研修だけでは足りない?よくある誤解を整理
「実務者研修=医療的ケアが全部できる」わけではない
よくある誤解のひとつがこれです。 「介護福祉士の実務者研修を修了すれば、喀痰吸引も胃ろう注入も全部できるようになるんでしょ?」 実は、これは半分正解で半分誤解です。
たしかに、実務者研修の中には「医療的ケア(たんの吸引・経管栄養)」の基礎知識やシミュレーションによる演習が含まれています。しかし、それだけでは実際に現場で利用者に対してケアを行うための実地研修(実際に医療的ケアを行う対象者に対する指導)が不足しているため、別途、特定行為業務従事者研修(1号・2号研修)を修了する必要がある場合がほとんどです。
例外もある|平成28年度以降の介護福祉士は?
平成28年度(2016年度)以降、介護福祉士国家試験の受験には「実務者研修の修了」が義務付けられました。 これに伴い、厚生労働省は「平成28年度以降に資格を取得した介護福祉士は、改めて追加の研修を受けなくても、一定の条件(医師の指示、事業所の実施計画等)のもとで医療的ケアを実施できる」としています。
✅ つまり…
- 平成28年度以降の介護福祉士:
- 実務者研修内で医療的ケアに関する基礎研修を受けているため、改めて「特定行為業務従事者研修(1号・2号研修)」を受けなくても制度上は喀痰吸引等を実施可能。
- それ以前の介護福祉士・無資格者等:
- 喀痰吸引等を実施するためには、別途「特定行為業務従事者研修(1号・2号研修)」の受講が必要。
ただし、いずれの場合も、現場での医療的ケアの実施は、事業所の判断、医師の指示書、適切な実施体制の整備が必須です。「研修を受けたから自由にやっていい」ということでは決してありません。
学校現場の「3号研修」って?教員が医療的ケアをするための制度
3号研修の対象と目的
「3号研修」は、特別支援学校などで医療的ケアが必要な児童・生徒に対応するため、教員が安全にケアを行えるように設けられた制度です。 対象となるのは、主に以下のような教職員:
- 特別支援学校の担任や副担任
- 学校で日常的に医療的ケアに関わる教員
- 必要に応じて支援員などの職員
この研修の目的は、医療的ケアを「看護師にすべて任せる」のではなく、学校生活における日常生活や学習の支援の一部として、教員も安全に関わる体制を整えることです。児童生徒が安心して学校に通い、充実した学びを得るための重要な制度といえます。
都道府県によって運用に差がある
3号研修は、文部科学省の制度ではありますが、実際の研修の実施主体は都道府県であり、実施体制や運用は各都道府県や学校によって違いがあるのが実情です。
- ある県では教員が積極的に医療的ケアに関わり、対応範囲も広い。
- 別の県では「原則、看護師対応」として教員は介助のみにとどめる、といった運用方針の違い。
このため、学校ごと・県ごとに運用方針の違いがあり、研修を修了していても「うちの学校ではまだ…」といった現場での混乱が起きやすいのが現実です。
現場とのギャップ|制度はあっても「実際どうすれば…?」の声が多い理由
指示書やマニュアルの整備が追いつかない
制度では研修を受けた職員が実施できるとされていますが、実際には、そのケアを実施するための「具体的な仕組み」が十分に整備されていないケースが多々あります。
- 医師の具体的な指示書がない(曖昧な指示しかない)
- 現場でケアの手順が示されたマニュアルが整備されていない
- 緊急時の対応手順が不明確
- 誰が最終的な責任を持つのか曖昧
などの理由で、研修を修了していても「安全に実施できない」「実施をためらってしまう」という声が聞かれます。
「責任の所在」が不明確になりやすい
特に医療的ケアの場合、少しの判断ミスが利用者の命に関わることもあるため、誰が何を判断し、誰が責任を持つのかを明確にしておく必要があります。
- 看護師が不在の時間は誰が責任を持つのか?
- 緊急時の連絡体制は?
- 判断に迷ったとき、誰に相談すればいいのか?
現場では「誰かがやってくれるだろう」「暗黙の了解」といった状態になりがちで、それが職員の大きなストレスや不安、時には事故の原因にもなっています。
まとめ|制度と実態の橋渡しをしていこう
1号・2号・3号研修は、医療的ケアを必要とする方々の生活を支えるために、制度として設けられた重要な枠組みです。 しかし、制度がある=すぐに安全に実施できるわけではありません。
- 実地での支援体制の構築
- チームでの密な連携
- 責任の明確化
- 利用者の安全と尊厳の確保
これらがそろって、はじめて制度が「生きたもの」として現場に根付きます。 この複雑な制度を「知っておくだけ」でも、きっと明日の支援が少し安心になるはずです。 そして、それぞれの立場の人が制度を正しく理解し、現場の課題を共有することで、より良い支援体制が構築されていくことを願っています😊
関連リンク

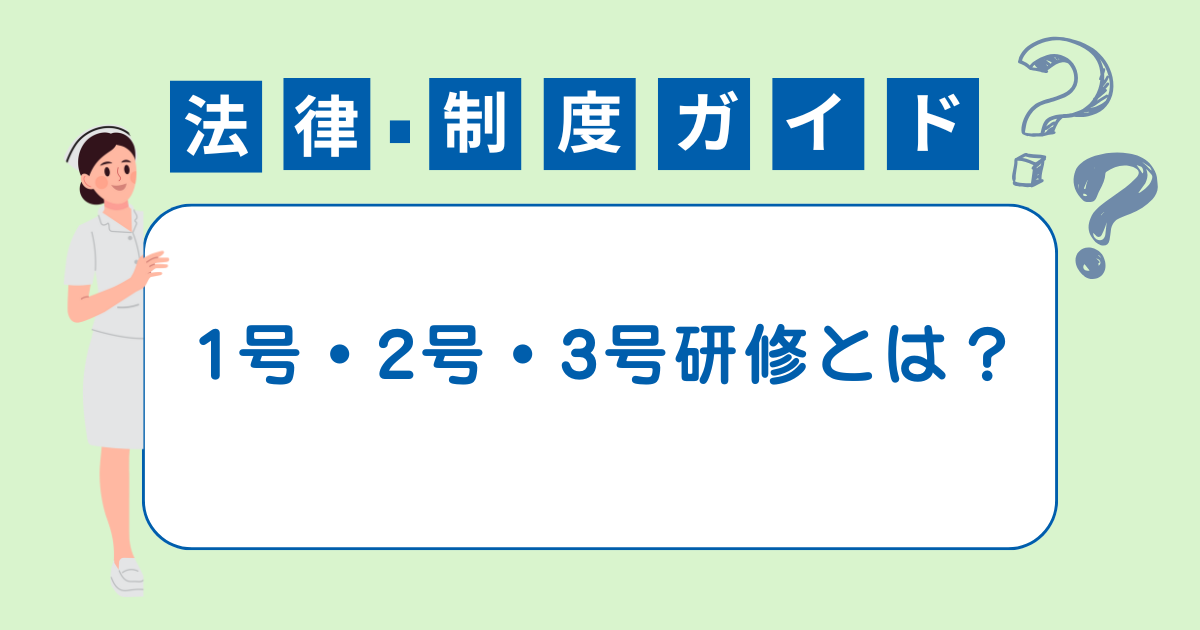

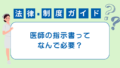
コメント