知らないと怖い“責任の所在”と現場トラブルのリアル解説
はじめに:なぜ「指示書」が医療的ケアの”鍵”なの?
医療的ケアに関わる現場でよく耳にする「医師の指示書」。 「書類が多くて面倒だな」「いつも通りやってるから大丈夫でしょ?」…そう感じたことはありませんか?
でも、この指示書は、医療的ケアを安全に、そして法的な根拠をもって行うための、まさに”命の証”とも言える重要な書類なんです。 「なぜ必要なのか」「もしなかったらどうなるのか」を知らないと、大きなトラブルや、最悪の場合「責任問題」に発展するリスクも潜んでいます。
この記事では、
✅ 医師の指示書とは何か?
✅ なぜ指示書が不可欠なのか?
✅ 実際に起きた「指示書なし」のトラブル事例
✅ 現場で困らないための対策とポイント
……などを、現場30年の看護師の視点から、わかりやすくリアルに解説します。
医師の「指示書」とは?法律上の“根拠”を徹底解説
医療行為の基本ルールと「診療の補助」
医師法第17条にはこう書かれています。
「医業は、医師でなければ行ってはならない」
つまり、医療行為は医師しかやってはいけない、というのが基本ルールです。 しかし、このルールには例外があります。それは、「医師の指示のもとで」看護師などが行える行為。これを「診療の補助」と言います。
そして、この「医師が確かに指示をした」という事実と、その「指示の内容」を客観的に証明する書類こそが、医師の指示書なのです。医療的ケアを行うすべての人にとって、この指示書が法律上の“根拠”となる、非常に重要な役割を担っています。
指示書にはどんな内容が書かれているの?
医師の指示書には、安全かつ適切に医療的ケアを実施するために、以下の詳細な内容が記載されています。
- 利用者(児・者)の名前、生年月日、基本情報
- 診断名や病状、現在の健康状態
- 必要な医療的ケアの種類(例:喀痰吸引、経管栄養、血糖測定、インスリン注射、気管切開部の管理など)
- 各ケアの実施方法の詳細や注意点(例:吸引の深さ・頻度、注入する栄養剤の種類・量・速度、使用する器具など)
- 異常時や緊急時の対応方法
- 医師名、所属医療機関名、連絡先
- 発行日と有効期限
有効期限は3か月から6か月のことが多いですが、利用者の状態変化に合わせて随時更新が必要です。 形式は自治体や施設、医療機関によって異なりますが、どんな形であっても医療行為を安全に実施するための法的根拠になる重要な書類であることに変わりはありません。
なぜ「指示書」が必要なの?「責任の所在」を明確にするため
法律的に必要不可欠な”証明”
くり返しになりますが、医師法に基づき、医療行為を医師以外が行うためには、明確な根拠が必要です。その根拠となるのが「医師の指示」であり、それを文書化した「指示書」なのです。
特に、介護職員や学校の教員など、看護師以外の職種が「喀痰吸引等研修」などを修了して医療的ケアに関わる場合は、研修の修了要件に加え、必ず医師の指示書と連携体制が必須となります。どの立場の支援者であっても、指示書がなければ、法的な問題に発展するリスクが伴います。
現場の“責任の所在”を明確にする
もうひとつの、そして最も重要な理由が、「万が一のときの責任の所在」を明確にするためです。 医療的ケアは、命に直結するデリケートな行為です。もしトラブルや事故が起きてしまった際、以下の点が曖昧なままだと、大きな問題になります。
- 誰の指示で、どのような方法でケアが行われたのか?
- その方法や頻度は、医師が判断し承認していたものか?
- ケア中に問題が起きた場合、最終的な判断責任はどこにあるのか?
「きちんと指示書をもらって、それに書かれた内容に正確に従って実施した」という記録があることで、医療的ケアを実施するスタッフだけでなく、それを管理する施設や学校側も法的に守られます。この「法的根拠」と「責任の明確化」があるからこそ、スタッフは安心してケアに取り組むことができるのです。
実際に起きた“指示書なし”のトラブル事例
「指示書がないとどうなるの?」という疑問に、実際に現場で起こりうるトラブル事例を交えて解説します。
例1:学校現場での吸引ミス〜「いつも通り」が落とし穴に〜
ある特別支援学校で、医療的ケア児を支援していた教員が、看護師の不在時に「いつもと同じ方法で口腔内の吸引」を実施しました。しかし、本人の体調がいつもと異なり、強い嘔吐と誤嚥が起きてしまいました。 その後の調査で明らかになったことは、恐ろしい事実でした。
- 医師の指示書が更新されておらず、有効期限が切れていた
- 保護者からの文書同意も曖昧なままだった
- 教員は「慣れていたから」「以前の指示で続けていた」と主張したが、法的には「自己判断で行った」ことになってしまい、責任を問われる事態に
このように、「慣れていたから」「いつもやっているから」という“善意”だけでは済まないのが医療的ケアです。法的根拠のない行為は、支援者自身を危険にさらします。
例2:施設での指示書の期限切れ〜監査で見つかった「見えないリスク」〜
とある高齢者施設では、長年経管栄養を行っていた利用者がいました。日々のケアは滞りなく行われていましたが、ある日、抜き打ちの内部監査が入りました。 その結果、「医師の指示書が8か月間、更新されていない」ことが発覚しました。 担当の看護師は「以前の指示の内容で継続していたので、問題ないと思っていた」と主張しましたが、監査側からは以下の点が厳しく指摘されました。
- 「指示書が切れた間に、利用者の状態変化があったかもしれないのに、医師の専門的な判断を仰いでいない」
- 「適切な期間で医師の判断を更新するという、医療安全上の義務を怠っていた」
結果として、施設管理者が厳重注意を受け、ご家族にも謝罪する事態に発展しました。これは、直接的な事故にはつながらなかったものの、「隠れたリスク」が放置されていた典型的なケースです。
現場で困らないために|対策とポイント
このようなトラブルを防ぎ、安心・安全な医療的ケアを行うためには、以下の対策とポイントをチーム全体で共有することが大切です。
① 指示書の更新と管理をルール化する
有効期限が切れないよう、徹底したスケジュール管理が必要です。
- 多くの施設では「年2回(6か月ごと)の更新」「更新月の1ヶ月前にアラート」などの仕組みを整備しています。
- 電子カルテや共有カレンダーなどのデジタルツールを活用し、リマインダーを設定するのもおすすめです。
- 新しい指示書を受け取ったら、必ず内容を確認し、古いものと入れ替えて保管しましょう。
② 新規入所・異動時の確認を忘れずに
新しい利用者を受け入れる際や、担当スタッフが異動した際には、まず指示書の有無と内容を必ず確認しましょう。
- 学校の場合、就学前に保護者を通じて主治医に指示書の発行を依頼してもらうケースが多いです。
- 「提出済みだと思っていた」「前の担当者が持っていると思っていた」が、実は未提出だったり、古い情報のままだったり…というのは非常によくあるトラブルです。最初の段階でしっかり確認することが肝心です。
③ チーム全体で「指示書の意味と重要性」を共有する
看護師だけでなく、医療的ケアに関わる全ての支援者(介護職、支援員、教員、ヘルパーなど)が、指示書の意味とそれぞれの責任範囲を理解することが不可欠です。
- 「あの人がいつもやってるから大丈夫」という属人的な判断は避けましょう。
- 「このケアは誰が、どんな根拠(指示書)に基づいて、どんな手順でできるのか?」を常に確認し、疑問があればすぐに共有できる習慣をつけましょう。
- 養護教諭や施設管理者も含めて「医療的ケアの実施体制全体」を定期的に共有し、見直すことが、安心・安全な支援につながります。
まとめ|指示書は“安心の土台”
医師の指示書は、ただの形式的な書類ではありません。 医療的ケアを安全に、そして法的にも安心して行うための揺るぎない土台であり、万が一のトラブルから私たち支援者を守る鍵なのです。
「面倒だから後回し」「いつものやり方で大丈夫」 …そんな油断が、取り返しのつかないリスクを生むこともあります。
でも逆に、指示書が適切に整備され、チーム全体でその重要性を理解していれば、現場はとても守られ、安心してケアを提供することができます。
新しい利用者が来たとき、ケアの方法に変化があったとき、あるいはチームで役割を再確認するとき。 そんな時には、ぜひ一度、指示書を見直し、その内容と意味を深く理解してみてくださいね。
関連リンク

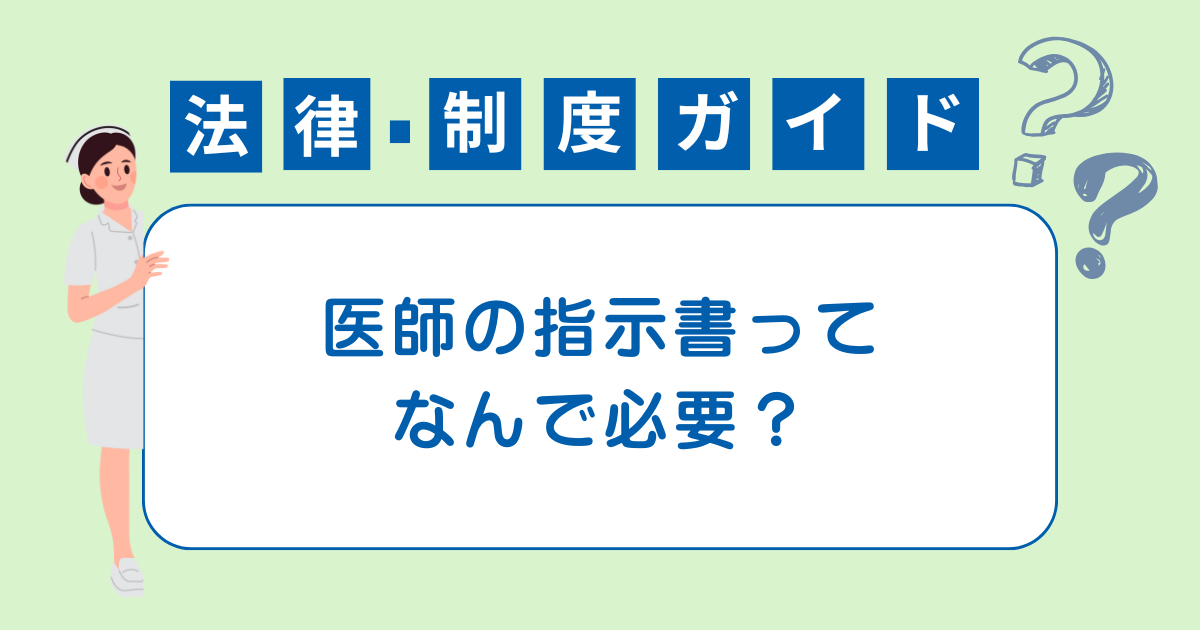


コメント