医療的ケアの「責任」とは誰にあるのか?
医療的ケアに関わる現場で、いつもついてまわるのが「責任」という言葉。
「もし何かあったら、誰が責任をとるの?」 「どこまで判断していいの?」
…そんな不安や疑問を、現場で感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
医療的ケアは命に係わる行為だからこそ、医師や看護師のみならず、関わるすべての人に「法律的な義務」や「責任の所在」がしっかりと定められています。 そして責任とは、「自分に任された役割をきちんと果たしたか?」を問われること。そして、それは法的、倫理的、専門的にさまざまな視点から発生します。
この記事では、
✅ 医療的ケアにおける“責任”の法的根拠
✅ 法律上の義務と各機関・職種の具体的な役割
✅ 緊急時に求められる「判断」と「行動」の範囲
✅ トラブルを防ぐための連携と体制整備のポイント
…を、現場経験をもとにわかりやすく解説していきます。
医療的ケアの「責任」とは?法的根拠を整理
医師法と看護師法に見る“医療行為”の基本原則
医療的ケアの責任を語るとき、まず基本になるのは「医師法第17条」です。
「医師でなければ、医業をなしてはならない」
つまり、原則として医療行為(医業)は医師しかできません。 しかし、この原則には「例外」があります。それが、「保健師助産師看護師法(看護師法)第5条」で認められている、看護師による「診療の補助」です。
【看護師法第5条(抜粋)】 「この法律において『看護師』とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。」
これにより、看護師は医師の指示のもとで医療的ケアを行うことが法的に認められています。この「医師の指示」と「看護師の診療の補助としての役割」の明確化が、個々のケアの法的根拠、すなわち“責任の出発点”となるのです。
介護職員等・教員等への拡がりと「特定行為」
さらに、平成24年(2012年)の「社会福祉士及び介護福祉士法」等の改正により、一定の研修(喀痰吸引等研修1号.2号.3号について解説)を修了した介護職員や、特別支援学校の教員等も、医師の指示および事業所・学校の適切な実施計画に基づき、一部の医療的ケア(特定行為)を実施できるようになりました。
この制度は、「医療的ケアを必要とする方の生活の場を支える」という社会的要請に応えるためのものです。ただし、ここでも重要なのは「資格の範囲を超えないこと」と「安全確保の責任」です。
緊急時に起きる“判断の迷い”|その場でできること・できないこと
緊急時対応の原則:「緊急避難」と「安全確保」
急な体調変化、呼吸器トラブル、意識低下など、医療的ケアが必要な方には予測不能な事態が起こり得ます。このような時、即座の対応が求められますが、現場で働く人が「どこまで対応してよいのか」は大きな迷いとなります。
【現場で求められる対応の切り分け】
- 「その場でできること(一次救命処置の範囲内)」:
- 周囲の安全確保: まず自身の安全、周囲の安全を確保する。
- 状況の確認と声かけ: 意識、呼吸状態、顔色、苦痛の有無などを冷静に観察し、声をかける。
- 応援要請: すぐに医療職(看護師、医師)や管理者に連絡し、応援を求める。
- 体位保持・体温調整: 呼吸が楽になる体位を取らせる、衣類を緩める、体温を調整するなど、状態悪化を防ぐ処置。
- 一次救命処置(BLS): 心肺蘇生法(胸骨圧迫)、AEDの使用、異物除去など、すべての人が習得すべき基本的な救命手技。
- 記録: 発生時刻、状況、行った対応、連絡先などを正確に記録する。
- 「原則として専門職の指示や判断が必要なこと」:
- 医療的判断を伴う処置: 投薬、点滴、人工呼吸器の設定変更など、医師・看護師の専門的な判断や指示なしに行う医療行為。
- 資格・研修範囲外のケア: 喀痰吸引等研修を修了していない者が吸引を行う、経管栄養を実施する(緊急避難と認められる場合を除く)。
- 自己判断での処置の変更: 指示書にない方法でケアを行う、勝手に医療機器の設定を変える。
基本原則は、「救命」と「安全確保」です。 法的には「緊急避難」(刑法第37条等に規定)の原則があり、差し迫った危険から生命・身体を守るためにやむを得ず行った行為は、違法性が問われない場合もあります。しかし、これはあくまで最終手段であり、日頃の体制整備が最も重要です。
各機関・職種の役割と責任の違い
医療的ケアにおける責任は、一人に集中するものではなく、それぞれの機関・職種が担う役割と義務によって分担されています。
1. 医師:最終的な医療判断と指示・管理の責任
- 医療行為の可否判断: 医療的ケアの開始・中止、方法、頻度など、すべての医療行為に関する最終的な判断を行います。
- 指示書の作成と更新義務: ケア内容、手順、緊急時対応など、具体的な実施方法を記載した指示書(指示医の氏名、有効期限の明記必須)を発行し、利用者の状態変化に合わせて定期的に更新する義務があります。これは医療的ケアを他職種が実施する際の法的根拠となります。
- 医療的ケア全体の管理責任: 医療的ケアが安全かつ適切に実施されているかを管理・監督する責任を負います。
2. 看護師:実施者としての専門的責任と他職種連携の要
- 医師の指示に基づく実施義務: 医師の指示書に基づき、安全かつ正確に医療的ケアを実施する専門的な責任を負います。
- 状態観察とアセスメント: 利用者の状態を継続的に観察し、異常の早期発見に努め、必要に応じて医師に報告・相談する義務があります。
- 他職種への指導・助言: 介護職員や教員などに対し、適切なケア方法や観察ポイントについて指導・助言を行う責任があります。
- 緊急時の判断と対応: 医師への報告・連絡・相談に加え、状況に応じて医師の指示を仰ぎながら初期対応にあたります。
3. 教員・介護職員・支援員:研修と指示に基づく実施者としての責任
- 研修修了と指示書に基づく実施: 喀痰吸引等研修(1号・2号・3号)を修了し、かつ医師の指示書、事業所・学校の実施計画に基づいている場合にのみ、認められた範囲の医療的ケアを実施する責任があります。
- 実施範囲の厳守: 自分の資格や研修で認められた範囲を逸脱しないことが最重要です。指示書にないケアや、判断を要するケアは行いません。
- 異常時の報告義務: 利用者の体調やケアの状況に異変があった場合は、速やかに看護師や医師、管理者に報告する義務があります。無理に自己判断で対応せず、専門職にバトンを渡すことも重要な責任の一部です。
4. 管理者・事業者(施設長・学校長など):安全管理体制整備の義務
- 実施体制の整備義務: 医療的ケアを安全に実施するための人員配置、設備、環境を整える法的義務があります(医療的ケア児支援法、介護保険法、障害者総合支援法など)。
- 医師の指示書・同意書の管理: 利用者ごとの医師の指示書、保護者や利用者からの同意書を適切に管理し、常に最新の状態を保つ責任があります。
- 緊急時マニュアルの策定と周知: 緊急時対応の手順を明確にしたマニュアルを作成し、全職員に周知徹底する義務があります。定期的な訓練(シミュレーション)の実施も重要です。
- 外部との連携・報告体制の構築: 医療機関、行政、家族などとの連携体制を構築し、インシデント・アクシデント発生時の報告義務を果たします。
トラブルを防ぐ「責任の見える化」チェックリスト
現場で「責任の所在」を明確にし、トラブルを未然に防ぐためには、以下の点を定期的に確認・共有することが有効です。
- 指示書と同意書の整備と管理: 全ての医療的ケアについて、有効な医師の指示書と利用者・保護者の同意書があるか?
- 職員の研修履歴・資格確認: 医療的ケアを実施する職員が、適切な研修を修了し、資格があるか?
- 緊急時対応マニュアルの策定と共有: 緊急時の手順が明確で、全職員が内容を理解し、実際に訓練されているか?
- 異常時の報告体制の明確化: 誰に、どの順で、どのように報告するか(ヒヤリハットを含む)がルール化されているか?
- 看護師不在時の対応ルール: 看護師が不在の際に、誰がどこまで対応し、誰に連絡するのかが明確か?
- 定期的カンファレンス・情報共有: 関係者(医師、看護師、介護職、教員、家族など)間で定期的に情報共有が行われているか?
責任は“押しつけ合い”ではなく“支え合い”
医療的ケアに関わるすべての人に、それぞれの「責任」と「法的義務」があります。 しかし、それは「ひとりで抱え込む」ものではなく、「チームで連携し、支え合って守る」ものです。
責任の所在を明確にしながら、それぞれの立場でできること・すべきことを理解しておけば、いざという時も、落ち着いて行動することができます。 緊急時に迷わず、安全に、そして安心してケアを提供するためにも、日頃から「責任と法的義務」をチーム全体で共有し、確認しておくことが重要です。
その積み重ねが、医療的ケアを必要とする利用者にとっても、日々を支える支援者にとっても、安心と信頼につながるのです。
関連リンク

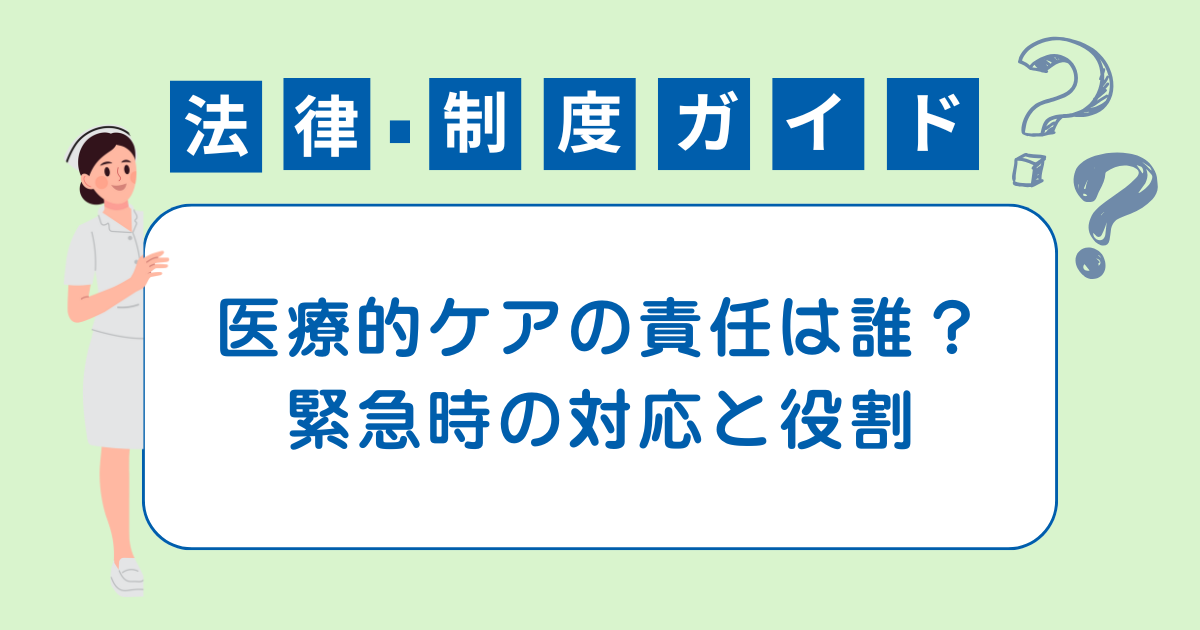
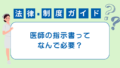
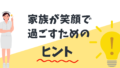
コメント