医療的ケア児との暮らし、一人で抱え込まないで
医療的ケア児と過ごす毎日は、かけがえのない喜びと同時に、多くの戸惑いや大変さを伴うものです。 「このケアで合っているのかな?」「将来はどうなるんだろう」「なんだか疲れてしまった…」 そんなふうに、一人で抱え込んでしまうこともあるかもしれません。
でも、日々のちょっとした工夫や、利用できる支援制度をうまく活用することで、家族みんなが笑顔で過ごせる時間を増やすことができます。
この記事では、現役看護師長として医療的ケア児支援に関わってきた経験から、
✅医療的ケア児と暮らす日常生活で役立つヒント
✅知っておきたい支援制度のポイント
などを分かりやすくご紹介します。
家族が笑顔で過ごすための「暮らしのヒント」
毎日の「安心」につながる生活リズムの整え方
医療的ケア児は体調の変化が起きやすい特性があるため、可能な範囲で規則正しい生活リズムを意識することが大切です。
例えば、毎日の食事やケアの時間を大まかに決めておくことは、お子さん自身が安心して過ごせることにつながるかもしれません。 また、ご家族にとってもケア計画を立てやすくなる一つの方法です。
もちろん、体調が悪い時などは無理せずに過ごしましょう。
家族みんなで支え合う「チームケア」のすすめ
医療的ケアは、一人だけに負担が集中すると心身ともに疲弊してしまいます。
できる範囲で家族が協力しあい、それぞれの役割を持つことが大切です。
例えば、兄弟姉妹が簡単なこと(ケア用品を渡す、見守るなど)で関わることで、家族全体の絆も深まり、お子さんへの理解も深まるかもしれないですね。
ケア環境を整えて「スムーズな毎日」を
医療機器や消耗品の管理は、日々のケアをスムーズに進める上で非常に重要です。
- 整理整頓を心がけ、必要なものがすぐに取り出せる場所に置く。
- 緊急時に備え、予備品や連絡先リストをすぐに確認できる場所にまとめておく。
- 感染対策のため、清潔な環境を保つ。
これらの工夫で、急な対応も落ち着いて行えるようになるでしょう。
医療的ケア児の子育てで「ストレスをためない心構え」
「完璧」より「継続」を!自分を労わって
日々のケアは完璧でなくても大丈夫です。
医療的ケアはマラソンのようなもの。毎日を継続していくことが最も大切です。 時には「今日は手を抜いてもいいか」と自分に許可を与えることも、長く続けるためには必要です。
ケア者自身の「心のゆとり」を大切に
ご家族が笑顔でいるためには、ケアを担う方自身のリフレッシュがとても大切です。
- 短時間でも自分の好きなこと(趣味、読書、散歩など)に時間を使う。
- 信頼できる友人や家族と話す時間を作る。
無理なく自分の時間を確保し、心身の健康を保つように意識しましょう。
仲間とつながり「孤立」を防ぐ重要性
同じ境遇の家族と交流することは、情報交換だけでなく、何より精神的な支えになります。
- 地域の医療的ケア児支援グループや、オンラインコミュニティ(SNSなど)を活用してみましょう。
- 「わかる」人がいるだけで、孤独感が和らぎ、新たなヒントが見つかることもあります。
医療的ケア児の家族が利用できる「支援制度とサービス」
医療的ケア児とそのご家族を支えるための公的な制度やサービスが整備されています。積極的に活用を検討しましょう。
障害児通所支援サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)
- 目的と内容:
- 児童発達支援:未就学の医療的ケア児が、発達を促すための療育や集団活動を行う場です。専門スタッフによる個別支援や集団生活を通じて、心身の発達をサポートします。
- 放課後等デイサービス:就学後の医療的ケア児が、学校の授業終了後や長期休暇中に利用できるサービスです。生活能力向上のための訓練や余暇活動を提供し、居場所づくりを支援します。
- メリット: お子さんの成長を支援し、ご家族のレスパイト(一時休息)にもつながります。
訪問看護サービス(医療保険・障害者総合支援法)
- 目的と内容:
- 看護師や理学療法士、作業療法士などがご自宅を訪問し、医療的ケア(喀痰吸引、経管栄養など)の実施、健康状態の観察、リハビリテーションなどを提供します。
- 対象となる法律: 医療的ケア児の場合、主に医療保険が適用されます。 また、障害者総合支援法に基づくサービス(居宅介護、重度訪問介護など)の中で、医療的ケアを伴う身体介護などが提供される場合もあります。 ※18歳以上になると、介護保険の優先適用が検討される場合もあります。
- メリット: 自宅で専門的な医療ケアを受けられ、ご家族のケア負担を軽減できます。看護師にケアを任せて、その間に買い物に出かけたり、自分の時間を確保するといった利用も可能です。緊急時にどう対応したらいいかなどの相談も可能です。
ショートステイ(短期入所)や日中一時支援の活用
- 目的と内容:
- ショートステイ(短期入所):医療的ケア児が一時的に施設に入所し、医療的ケアを含めた生活支援を受けるサービスです。ご家族が病気や冠婚葬祭、あるいは一時的な休息を取りたい場合などに利用できます。
- 日中一時支援:日中に医療的ケア児を預け、生活能力向上のための訓練や活動支援を受けるサービスです。ご家族が日中に用事を済ませたり、休息を取ったりする際に利用できます。
- 対象となる法律: いずれも障害者総合支援法に基づくサービスです。
- メリット: ご家族の身体的・精神的負担を軽減し、レスパイトケア(一時的な休息)を確保するために非常に有効です。行政によって利用できるサービスや条件が異なる場合があるため、お住まいの自治体窓口への相談が重要です。
障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)の活用
- 目的と内容: 医療的ケア児の場合、多くは身体障害者手帳の取得対象となります。手帳の等級に応じて、さまざまな福祉サービスや割引制度(税の控除、公共交通機関の割引など)を利用できるようになります。
- メリット: 福祉用具の給付・貸与、手当の受給、医療費助成、公共料金の割引など、経済的・生活的な支援を受けられます。
各地域の「相談窓口」を積極的に活用しよう
どこに相談すればいいか迷ったら、まずはお住まいの地域の以下の窓口に連絡してみましょう。
- 自治体の福祉課(障害福祉担当):地域で利用できるサービスや手当、制度に関する総合的な相談窓口です。
- 医療的ケア児支援センター:医療的ケア児支援法に基づき設置が推進されている専門の相談窓口です。多職種連携の中心となり、医療・福祉・教育の様々な相談に応じ、適切な支援につなげてくれます。
- 保健所・保健センター:乳幼児期の健康相談や発達相談などを受け付けています。
一人で抱え込まず、支え合いながら笑顔の毎日へ
医療的ケア児の子育ては、時に大きな困難を伴うことも事実です。しかし、日々の暮らしの中でできる工夫や、国の医療的ケア児支援法をはじめとする適切な支援制度・サービスを賢く利用することで、ご家族みんなが笑顔で過ごせる時間を確実に増やすことができます。
一人で全てを抱え込まず、専門機関や仲間とつながり、支え合いながら少しずつ進みましょう。 あなたの笑顔が、お子さんの、そして家族みんなの笑顔につながるはずです。
関連リンク

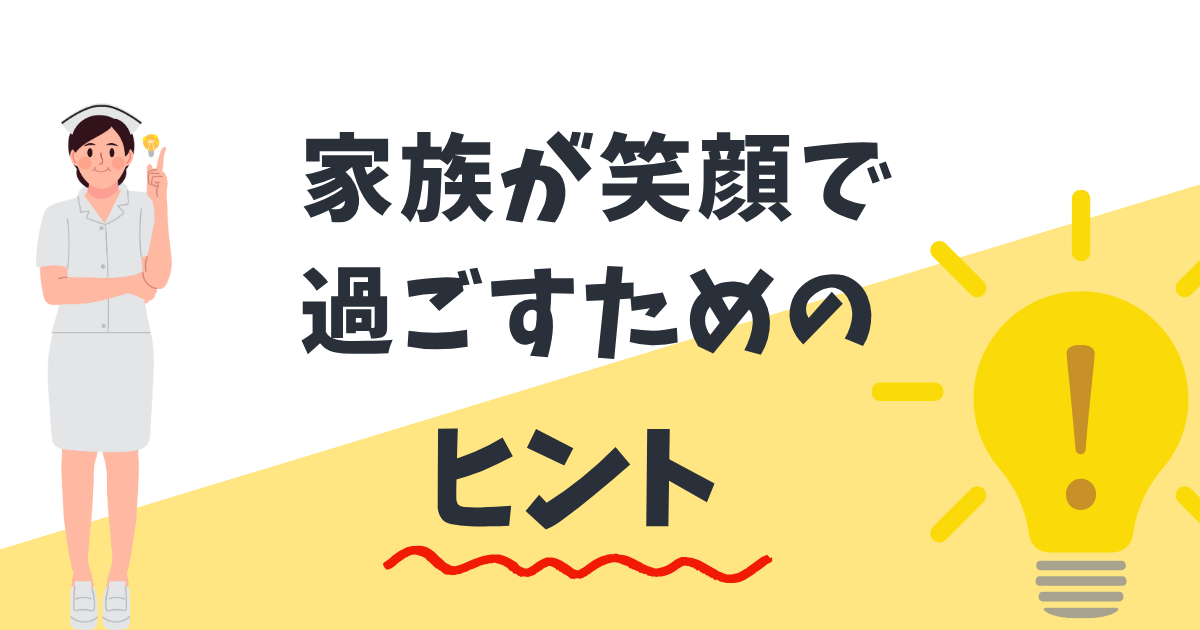


コメント