医療的ケア児を育てるご家族や、支援者の皆様。 日々の喀痰吸引、本当にお疲れ様です。慣れているつもりでも、時としてヒヤリとする瞬間はありませんか?特に「痰が取れない」という状況は、お子さんの苦しそうな様子を見ると、胸が締め付けられる思いになることでしょう。
私自身、30年以上現場の看護師として、多くの医療的ケア児とそのご家族を見てきました。この経験から、痰が取れない時の親御さんの焦りや不安を痛いほど理解しています。
この記事では、そんな「痰が取れない」という緊急時にどう対応すれば良いのか、具体的な【緊急対処法】と、そうなる前にできる【予防策】について、現場看護師の視点から詳しく解説します。
少しでも皆様の不安が和らぎ、日々のケアに自信を持てる一助となれば幸いです。
「痰が取れない!」その時、焦らず確認すべきこと
「痰が取れない!」その時、確認すべきこと
痰が取れないと感じた時、まず冷静になることが大切です。焦りはミスを招く可能性があります。 以下の点を順に確認し、状況を判断しましょう。
- お子さんの状態: 呼吸の状態はどうか?(ゼーゼー、ヒューヒューしているか、呼吸は苦しそうか、顔色はどうかなど)
- 吸引チューブの状態: チューブがねじれていないか、吸引器との接続はしっかりしているか。
- 吸引器の電源・設定: 電源は入っているか?吸引圧は適切か?(設定が低いと十分に吸引できません)
- 吸引カテーテルの種類・太さ: 適切でない太さや固さのカテーテルだと、奥まで届かない、痰が詰まりやすいなどの問題が起こることがあります。
- 痰の性状: 痰が粘っこいか、固いか、量が多すぎるか。
これらの確認と並行して、これから説明する「緊急対処法」を試していきます。
医療的ケア児の喀痰吸引「痰が取れない時」の【緊急対処法】
ここからは、実際に痰が取れにくいと感じたときに試してほしい具体的な対処法です。
(1) 体位変換を試す
お子さんの体位を変えることで、痰の位置が変わり、吸引しやすくなることがあります。
- 側臥位(横向き): 上を向いたままでは痰が喉の奥に留まりやすい場合、左右の横向きにすることで、痰が動きやすくなることがあります。重力を利用し、肺の奥の痰も移動させやすくします。
- 座位(座った姿勢): 可能であれば、上体を起こすことで気道が広がり、痰の移動が促されます。
- 腹臥位(うつ伏せ): 医師や理学療法士に相談し、安全に実施可能であれば、うつ伏せの姿勢をとることで、背中側の肺に溜まった痰を移動させやすくなることがあります。
(2) 呼吸介助を行う
お子さんの呼吸に合わせて、胸郭を軽く圧迫したり、サポートしたりすることで、痰の移動を促すことがあります。
- 胸郭のサポート: お子さんが息を吐くタイミングで、胸郭を軽くサポートするように手を添え、優しく呼吸を介助します。
- 力の加減: 強い力は加えず、お子さんに負担がかからないよう、必ず医療従事者から指導を受けた範囲で行ってください。
(3) 吸引圧の再確認と調整
吸引器の吸引圧が低すぎると、十分な吸引力を得られません。
- 設定圧の確認: 普段設定している吸引圧が正しいか確認してください。
- 一時的な調整: 医師や看護師の指導のもと、一時的に吸引圧をわずかに上げることで、粘度の高い痰を吸引できる場合があります。ただし、上げすぎると粘膜を傷つけるリスクがあるため、必ず専門家の指示に従ってください。
(4) 吸引カテーテルの交換または再挿入
- カテーテルの詰まり: 吸引中に痰がカテーテル内部に詰まって吸引力が落ちることがあります。新しいカテーテルに交換してみてください。または、しっかり通し水を吸ってみてください。
- 挿入深度の確認: カテーテルが奥まで届いていない可能性もあります。医師や看護師に指示された適切な深さまで、慎重に挿入できているか確認してください。無理な挿入は粘膜損傷のリスクがあります。
(5) 深い呼吸を促す(可能であれば)
お子さんが自力で深い呼吸ができる状態であれば、ゆっくりと深呼吸を促すことで、痰が移動しやすくなることがあります。無理強いはせず、お子さんの様子を見ながら行いましょう。
(6) 最終手段:医療機関への連絡・救急要請
上記の対処法を試しても改善が見られず、お子さんの呼吸状態が悪化している(顔色が悪い、呼吸が速い・浅い、意識状態が悪いなど)場合は、迷わずかかりつけ医、訪問看護師、または救急車(119番)に連絡してください。
「痰が取れない」を予防する!日々のケアのポイント
緊急事態を避けるためには、日頃からの予防的なケアが非常に重要です。
(1) 十分な水分補給と加湿、そして吸入の活用
- 水分補給: 体内の水分が不足すると痰が固くなり、吸引しにくくなります。医師や栄養士の指示に基づき、経口摂取や経管栄養などで十分な水分を補給しましょう。
- 適切な加湿: 部屋の湿度を適切に保つ(50〜60%を目安)ことで、気道粘膜の乾燥を防ぎ、痰を柔らかく保つことができます。加湿器の活用や、濡れタオルを干すなどの工夫も有効です。
- 吸入器の活用: 医師から処方されている吸入器があれば、指示された通りに活用することで、気道が潤い、痰が柔らかくなり、排出しやすくなります。 吸入は痰の性状を良好に保つ上で非常に有効な手段です。使用方法やタイミングについては、必ず医師や看護師の指導に従ってください。
(2) 定期的な体位変換とリハビリ、専門家との連携
- 定期的な体位変換: 寝たきりの時間が長いお子さんの場合、定期的に体位を変えることで、肺の同じ場所に痰が溜まるのを防ぎます。
- リハビリテーションの活用: 理学療法士や医師と相談し、お子さんの状態に合わせた呼吸介助や、効果的な体位(腹臥位など)の指導を受けましょう。 痰を排出しやすくするための専門的なケアについてアドバイスを得ることが、予防に繋がります。
(3) 正しい吸引手技の習得と定期的な見直し
- 医療従事者からの指導: 定期的に訪問看護師や病院の看護師から、最新の正しい吸引手技の指導を受けましょう。自己流にならないよう、疑問点があればその都度確認することが大切です。
- カテーテルの選定: お子さんの状態や痰の性状に合った、適切な太さ・種類・固さのカテーテルを使用することが重要です。
(4) 環境整備と感染予防
- 清潔な環境: 部屋を清潔に保ち、ウイルスや細菌の感染を防ぐことが、痰の増加や性状悪化の予防につながります。
- 手洗い・消毒: 吸引前後の手洗いや消毒を徹底し、清潔操作を心がけましょう。
(5) 痰の性状・量の観察と記録
- 日々の記録: 痰の色、量、粘稠度(ねばり具合)、臭いなどを毎日記録することで、お子さんの体調の変化や痰の状態の変化を早期に察知できます。
- 変化の共有: 変化に気づいたら、かかりつけ医や訪問看護師に速やかに共有し、適切なアドバイスを求めましょう。
まとめ:大切なのは「早めの対処」と「予防」、そして「専門家との連携」
医療的ケア児の喀痰吸引は、ご家族や支援者にとって大きな責任と不安を伴うケアです。「痰が取れない」という状況は誰にでも起こり得ます。
大切なのは、焦らず冷静に状況を判断し、学んだ【緊急対処法】を試すこと。そして何よりも、日々の【予防策】を丁寧に行い、医師や理学療法士、訪問看護師など専門家と密に連携を取りながらケアを進めることです。お子さんが快適に過ごせる時間を増やすことが一番大切です。
私のような現場看護師の経験が、皆様の安心に少しでも繋がれば幸いです。もし不安なこと、疑問なことがあれば、一人で抱え込まず、必ず医療機関や訪問看護師、地域の支援者にご相談ください。
【みつばスタイルからのお知らせ】
当ブログでは、医療的ケアに関する信頼できる情報源をまとめた「お役立ちリンク集」も公開しています。困った時に役立つ情報が満載ですので、ぜひご活用ください。
関連リンク

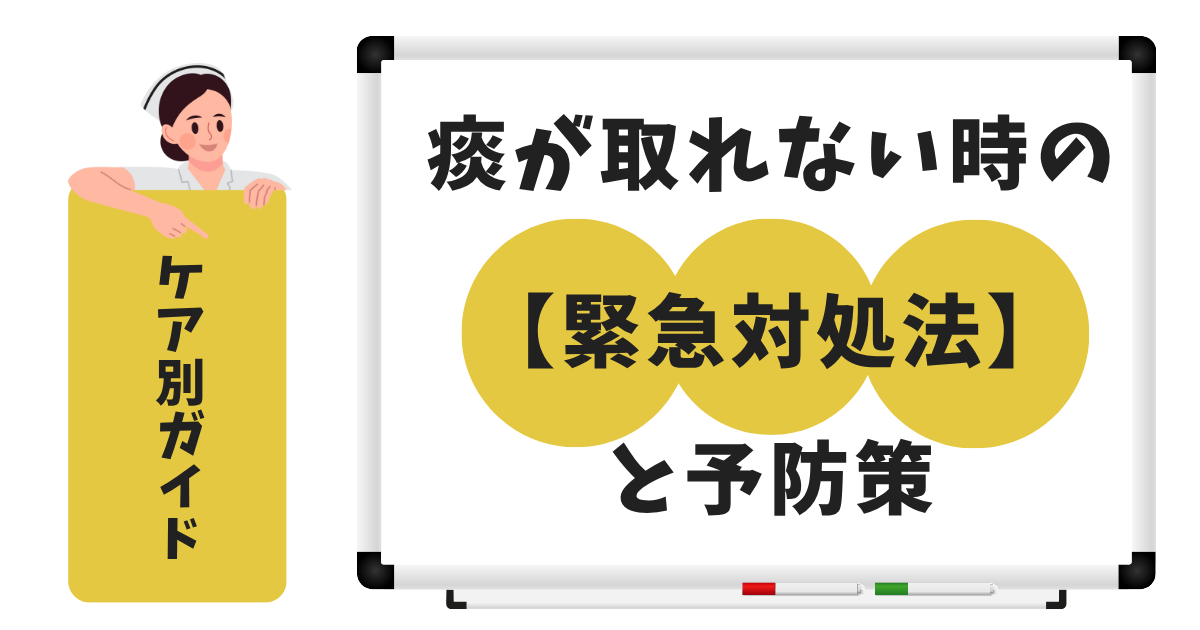

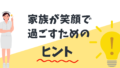

コメント