はじめに
はじめまして。このブログを読んでいるあなたは、今まさに「胃ろう」という言葉に不安や疑問を感じているかもしれません。
「胃ろうを作ったら、もう食べられなくなるの?」「在宅での介護って大変そう…」
そんなふうに身構えてしまうのは、決して不思議なことではありません。
でも、胃ろうは決して「終わり」ではなく、その人らしい暮らしを続けるための大切な選択肢なんです。
この記事では、看護師の視点から、胃ろうのある生活のリアルをQ&A形式で分かりやすくお伝えします。読者の皆さんの「知りたい」に、一つひとつ丁寧にお答えしていきますね。
Q1:「胃ろうがある=食べられない」って本当?
答えは「NO」です。
嚥下(えんげ:飲み込み)の機能が残っていれば、口から食べることも可能です。
実際の生活ではこんなスタイルがあります。
- 基本は口から食べるけど、薬や水分だけ胃ろうから
- 食べる量が少ないので、補助として胃ろうを併用
- 誤嚥のリスクがあるから、安全第一で胃ろうをメインに
つまり、胃ろうを作る=食べる楽しみを全部手放す、ではありません。「安全に」「その人らしく」食べる工夫ができるんです。
Q2:「胃ろうのある生活」って、1日の流れはどんな感じ?
胃ろうの注入は、その方の生活リズムに合わせて調整が可能です。
たとえば、1日3回、食事の代わりとして注入することが多いですが、体調や家庭の事情に合わせて回数や時間を自由に決めることができます。最初は少し緊張するかもしれませんが、繰り返すうちに「ご飯の準備」をするのと同じように、ごく自然な日常の一部になっていきますよ。
注入の基本的な流れ
- 手洗い・準備: 清潔な手で、栄養剤や器具の準備をします。
- 体位の確保: 注入中は、上体を30度以上に起こした状態をキープするのが理想です。
- 注入: 注入に要する時間は、栄養剤の種類や量によって変わります。
- フラッシュ(洗浄): 注入後にぬるま湯でチューブ内を流し、詰まりを防ぎます。
- 注入後の体位: 注入が終わった後も、30分〜1時間ほどは上体を起こした状態を保つようにしましょう。
【具体的なタイムスケジュールの一例】
※このスケジュールはあくまでも一例です。水分や栄養剤の量や回数は、年齢や体重、医師の指示によって変わります。必ず主治医や看護師などの指示を受けてください。
- 朝食(7:30): ラコール1袋(200ml)+白湯(200ml)
- 午前中(適宜): 麦茶(200ml)
- 昼食(12:00): ラコール1袋(200ml)+白湯(200ml)
- 午後(適宜): 野菜ジュース(100ml)+白湯(100ml)
- 夕食(18:00): ラコール1袋(200ml)+白湯(200ml)
といったように、「3回食」のリズムで過ごす方も多いです。
Q3:胃ろうを作ると、家での介護は大変になる?
「難しい手技なんじゃ…」と身構えるご家族は多いですが、実はとてもシンプルです。
- チューブの接続
- 栄養剤の注入
- フラッシュ(洗浄)
この流れさえ覚えれば、在宅でも十分対応できます。むしろ、鼻からチューブを入れる「経鼻経管栄養」よりも管理が楽になった!という声も多いです。
Q4:胃ろうをしている人に気をつけたいことは?
胃ろうのある生活で大切なのは、小さな変化に気づくことです。
よくあるトラブルと注意点をいくつかご紹介します。
- 皮膚トラブル: 発赤、ただれ、肉芽 → 日頃から皮膚を観察し、清潔を保つことが大切です。
- チューブ抜け: 自己抜去や固定不良 → 胃ろうの穴はすぐにふさがるため、早めの対応が必要です。
- 消化器トラブル: 嘔吐・下痢 → 注入速度や栄養剤の種類を見直すことで改善することもあります。
「いつもと違うな」と感じたら、一人で判断しようとせず、早めに主治医や看護師へ相談するのが安心です。
Q5:「もう○○できない」は思い込み?実はこんな工夫も!
「胃ろうがあるから、旅行はできない」「外出は無理」と思い込んでいませんか?
実際には…
- 栄養剤や注入キットを持っていけば、旅行や外出も可能です。
- 好きな味を口から少し味わうだけでも、生活の質(QOL)が向上します。
- 家族と一緒の食卓に座ることで、「食べる喜び」を共有できます。
胃ろうは“制限”ではなく、その人が安心して暮らすための“道具”なんです。
まとめ|胃ろうは「生きる選択肢」のひとつ
胃ろうを作ると、生活が大きく変わるように思うかもしれません。
でも実際には、「安全に栄養をとる」「その人らしい暮らしを続ける」ための大切なツールです。
- 胃ろうがあっても、食べる楽しみを残すことは可能
- 難しい手技ではなく、シンプルなケアで続けられる
- 大切なのは、その人の生活の質をどう守るか
不安や疑問があれば、一人で抱え込まず、遠慮なく医師や看護師に相談してくださいね。
胃ろうは「終わり」ではなく、新しい生活を支えるためのスタートです。

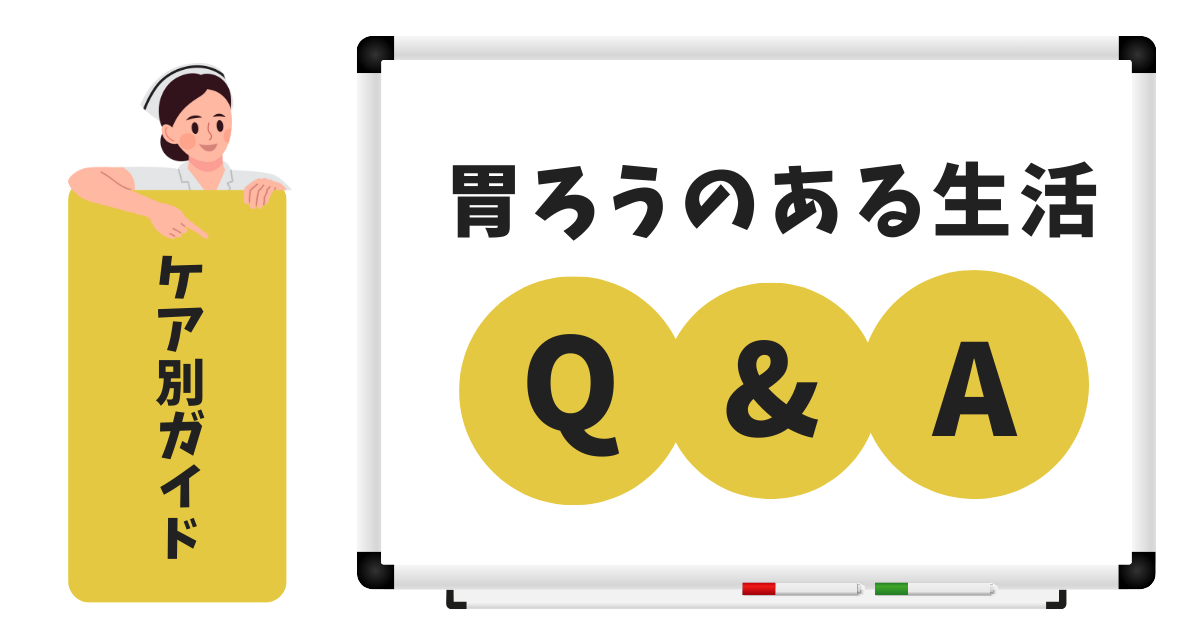
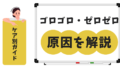

コメント