医療的ケア児のご家族や、在宅でのケアを検討されている皆様へ。
医療的ケア児との在宅生活では、訪問看護サービスが大きな支えとなります。しかし、「具体的にどれくらいの時間利用できるの?」「費用はどれくらいかかるの?」「複雑な制度でよく分からない…」といった不安や疑問を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
私自身、30年以上現場の看護師として、多くの医療的ケア児とそのご家族をサポートしてきました。訪問看護師とも密接に連携を取り、制度の利用に悩む親御さんの相談に乗る機会も多くありました。
この記事では、医療的ケア児の訪問看護サービスについて、利用できる時間の上限や、気になる費用負担の仕組みに焦点を当て、現場の視点も交えながら分かりやすく解説します。
複雑に感じられる制度を理解し、安心して訪問看護サービスを活用するためのヒントとなれば幸いです。
1. 医療的ケア児が利用できる訪問看護サービスとは?
訪問看護とは、看護師や理学療法士などがご自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて医療的ケアやリハビリテーションを行うサービスです。医療的ケア児の在宅生活を支える上で、欠かせない存在となっています。
主なサービス内容:
- 医療的ケア: 喀痰吸引、経管栄養、導尿、人工呼吸器管理、点滴管理、褥瘡ケアなど、多岐にわたる医療処置。
- 入浴介助: 人工呼吸器装着児など、特別なケアが必要な場合も含む入浴介助や清潔ケア。
- 健康状態の管理: 体温・血圧などのバイタルチェック、全身状態の観察、異常の早期発見と対応。
- 療養上のアドバイス: ご家族へのケア指導、病状や医療機器に関する相談、生活上の工夫など。
- リハビリテーション: 理学療法士や作業療法士による機能訓練(必要な場合)。
- 家族支援: 精神的なサポート、他のサービスとの連携調整など。
訪問看護サービスは、お子さんの病状や必要なケア内容に応じて、個別にケアプランが作成されます。
2. 医療的ケア児の訪問看護、利用できる時間の上限は?
訪問看護サービスの利用時間や頻度は、お子さんの病状や必要な医療的ケアの内容によって異なります。複数の制度を組み合わせることで、手厚い支援を受けることが可能です。
(1) 医療保険(医療的ケア児の場合は多くが対象)
- 制度: 主に「医療保険」が適用されます。(小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象疾患の場合も医療保険サービスの一環として利用)
- 利用時間:
- 基本的に週3回までが上限とされています。
- ただし、厚生労働大臣が定める疾病等(特定疾患、高度な医療管理が必要な状態など)に該当する場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合は、週4回以上、ほぼ毎日利用できるなど、大幅に利用回数が増える特例があります。医療的ケア児の多くはこの特例の対象となることが多いです。
- 【補足】特別訪問看護指示書について: 退院直後や病状の急変時など、一時的に頻回な訪問看護が必要な場合に発行されます。原則として14日間の短期集中支援に限られるケースが多いですが、医師の判断により月2回まで発行可能です。
- 1回の訪問時間は30分未満、30分以上1時間未満、1時間以上1時間30分未満など、複数の区分があります。
- 費用負担:
- 原則3割負担ですが、様々な助成制度(後述)により、自己負担が軽減されることがほとんどです。
(2) 介護保険(主に高齢者向けのため、医療的ケア児は通常利用しない)
- 制度: 高齢者向けのサービスのため、医療的ケア児は基本的に利用しません。
(3) 障害福祉サービス(地域生活支援事業、居宅介護など)
- 制度: 市町村が実施する「障害福祉サービス」の枠組みでも、訪問看護に相当するサービスを利用できる場合があります。
- 「居宅介護」の中の「重度訪問介護」や「行動援護」などが該当し、医療的ケアも含む身体介護や生活援助を長時間利用できることがあります。
- 利用時間:
- 自治体や個別のニーズに応じて、長時間(例えば、週に数十時間)の利用が可能な場合もあります。特に重度の医療的ケアが必要な場合は、24時間体制の支援につながるケースもあります。
- 医療保険だけではカバーしきれない部分を補う重要な役割を果たします。
- 【注釈】利用時間・上限額の地域差について: 障害福祉サービスの利用時間や月額上限額は、お住まいの市区町村によって差がある場合があります。また、都道府県によっては独自の加算(上乗せ支援)があるケースもありますので、必ずお住まいの自治体窓口で確認が必要です。
- 費用負担:
- 原則1割負担ですが、世帯の所得に応じた月額上限額(負担上限月額)が設定されており、それを超える自己負担はありません。
【ポイント】: 医療的ケア児の場合、多くは医療保険の特例や障害福祉サービス(重度訪問介護など)を組み合わせて利用することになります。お子さんの状態や家族の状況に合わせて、どちらの制度をメインにするか、どのように組み合わせるかを専門家と相談することが非常に重要です。
3. 知っておきたい【費用負担】の仕組みと助成制度
「どれくらいの費用がかかるの?」という疑問は、ご家族にとって最も大きな不安の一つでしょう。医療的ケア児の訪問看護利用には、様々な費用負担の軽減措置があります。
(1) 医療保険適用の場合の自己負担
- 原則3割負担: 医療保険適用の訪問看護は、原則として医療費の3割が自己負担となります。
- 高額療養費制度: 月々の医療費自己負担額が高額になった場合、「高額療養費制度」が適用され、所得に応じた自己負担限度額を超えた分は払い戻されます。この制度は、多くのご家庭の医療費負担を大きく軽減します。
(2) 障害福祉サービス適用の場合の自己負担
- 原則1割負担: 障害福祉サービスとして訪問看護(に準ずるサービス)を利用する場合、原則として費用の1割が自己負担となります。
- 月額上限額(負担上限月額): 障害福祉サービスには、世帯の所得に応じて「月額上限額」が定められています。
- この上限額を超えて自己負担が発生することはありません。例えば、月額上限が4,600円の場合、それ以上どれだけサービスを利用しても自己負担は4,600円までとなります。
- 所得が低い世帯ほど上限額は低く設定されています(0円の場合もあります)。
(3) 各種医療費助成制度の活用
医療的ケア児の場合、以下の医療費助成制度を活用することで、自己負担がさらに軽減されたり、実質無料になったりすることがほとんどです。
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度:
- 国が指定する16疾患群(786疾病)に該当するお子さんが対象です。
- 対象疾患の医療費(入院・外来・調剤・訪問看護など)の自己負担額が軽減されます。訪問看護もこの制度の対象となります。
- 所得に応じた自己負担上限額が設定されており、それを超える負担はありません。
- 自立支援医療(育成医療):
- 身体に障害がある児童が、その障害を除去・軽減するための医療を受けた場合、医療費の自己負担額を軽減する制度です。
- 対象となる医療行為(手術など)に関連する訪問看護が対象となる場合があります。
- 原則1割負担ですが、所得に応じた月額上限額が設定されています。
- 重度心身障害者医療費助成制度(自治体独自):
- 各自治体(都道府県や市町村)が独自に行っている医療費助成制度です。
- 身体障害者手帳1級・2級など、重度の障害を持つ方が対象で、医療費の自己負担分を助成してくれます。
- この制度の対象になれば、多くの医療費(訪問看護費用も含む)が実質無料になることが多いです。
【重要】: これらの制度は複雑に見えますが、必ずご自身が居住する市区町村の福祉担当窓口や、保健センター、または相談支援事業所に相談し、利用できる制度を把握し、申請手続きを進めるようにしましょう。
4. 訪問看護利用開始までの流れと相談先
訪問看護サービスを利用するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
- 相談・情報収集:
- 医療保険による訪問看護を検討している場合は、入院中の病院であれば退院調整看護師、医療連携室、または医療相談室に相談してください。
- **障害福祉サービス(重度訪問介護など)**の利用を検討している場合は、お住まいの市町村の障害福祉課や児童福祉課が主な窓口となります。
- 地域の保健師や相談支援事業所も、訪問看護の必要性や利用できる制度について情報収集を始める上で重要な窓口です。
- ケアプランの作成:
- 相談支援専門員(障害福祉サービスの場合)や訪問看護ステーションの担当者などと、お子さんの状態やご家族の意向に合わせたケアプランを作成します。
- 主治医の指示書:
- 訪問看護を利用するには、必ず主治医からの「訪問看護指示書」が必要です。
- 契約・利用開始:
- ケアプランと指示書に基づき、利用する訪問看護ステーションと契約を交わし、サービス利用開始となります。
【現場看護師からのアドバイス】: 「うちの子は利用できるの?」「どの制度を使えばいいの?」と悩んだら、まずはお子さんが入院中であれば病院の退院調整看護師や連携室・相談室へ、在宅で生活されている場合は、お住まいの市町村の障害福祉課・児童福祉課、地域の保健師さん、または相談支援事業所の専門員に相談してください。彼らは制度のプロであり、あなたの状況に合わせて最適なサービスを提案し、手続きをサポートしてくれます。一人で抱え込まず、専門家の力を借りましょう。
まとめ:訪問看護は在宅生活を豊かにする力強い味方
医療的ケア児の訪問看護は、お子さんの健康と成長を支え、ご家族の負担を軽減し、より豊かな在宅生活を送るための非常に重要なサービスです。
利用できる時間や費用負担の仕組みは一見複雑に思えますが、適切な制度を知り、活用することで、安心して質の高いケアを受けられるようになります。
最も大切なのは、一人で悩まず、積極的に医療機関や自治体、地域の専門機関に相談することです。 あなたの「みつばスタイル」ブログが、その一歩を踏み出す勇気と情報を提供できれば幸いです。
関連リンク

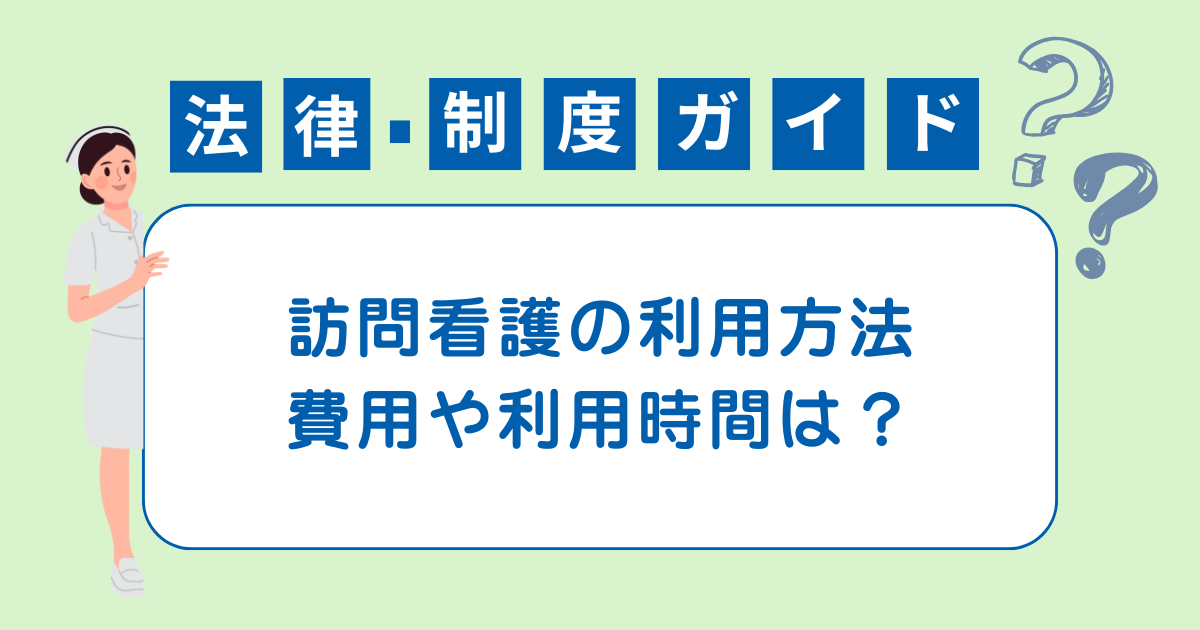


コメント