「何度吸引しても、ゴロゴロ・ゼロゼロという音が止まらない…」 在宅で喀痰吸引をされているご家族や支援者の方なら、誰もが一度は経験するお悩みではないでしょうか。
その音、本当に痰でしょうか?実は、その音の正体は痰ではないことも多く、闇雲に吸引を繰り返すと、かえって大切な人を傷つけてしまう可能性もあります。
この記事では、経験豊富な看護師の視点から、吸引しても止まらない音の「本当の正体」と、安全に判断・対処するための3つのポイントをわかりやすく解説します。
吸引しても止まらない“あの音”の本当の正体とは?
まず知っておいてほしいのは、 「ゴロゴロ=痰がある」ではないということ。
現場では、以下のような“痰以外”が原因のこともとても多いです。
よくあるケース:
- 鼻水が喉の奥に落ちて鳴っている
- 唾液が気道や喉で揺れている音
- 子ども本人が遊びで音を出している(ブクブクうがいのような音)
- 気道が狭く、吸気・呼気で音が鳴っている(狭窄音)
音が出ていても、必ずしも吸引が必要な痰とは限らないのです。
それ、痰じゃないかも?見極めるための3つのポイント
では、どうやって「これは吸引すべき音か、そうでないか」を見極めたらよいのでしょう?
① 全身状態を観察する
- 顔色、表情、機嫌はいつも通りか?
- 呼吸が苦しそうか?(肩で息をしている・陥没呼吸があるなど)
- 発熱や咳などの変化はあるか?
② 音の場所と性質を聞き分ける
- 鼻?喉?胸の奥?
- 低く湿った音か、乾いたヒューヒュー音か?
③ 吸引後の変化を確認する
- 音が変わったか?
- 吸った後も変わらないなら、痰ではなかった可能性も
無理な吸引はリスクにも。大切なのは「様子を見る」判断
吸引は必要なケアですが、必要以上に行うことでリスクもあることを忘れてはいけません。
- 粘膜へのダメージ(出血や傷)
- 嘔吐反射の亢進(吐きやすくなる)
- 子どものストレス(吸引=嫌なことと認識)
とくに、「いつもこの音がする」子の場合は、それが平常音(その子の特徴)であることもあります。
落ち着いているようなら、すぐに吸引せず“様子を見る”ことも大事な判断です。
🟡 プラスワンの対処法:体位を変える
吸引しても音が止まらないときは、横向きやうつ伏せなどの体位変換も効果的な方法です。
のどや鼻の奥にたまった鼻水や唾液が、自然と排出されやすくなるため、音が軽減・消失することがあります。
これは、
- 嚥下機能が未熟だったり
- 唾液や鼻水の分泌が多くてうまく処理しきれない子 に多く見られる現象です。
健康な人なら自然に飲み込むことで処理できるものも、医療的ケア児ではたまりやすく、音として現れます。
🔶注意点
ただし、唾液の分泌が多く、ゴロゴロ音とともにSpO2(血中酸素飽和度)が下がるような場合は注意が必要です。
唾液が気管に垂れこんでいることがあり、
- 酸素が下がっているときは呼吸状態が悪化する前触れかも。注意が必要です
- 持続吸引などの対応が必要なケースもあるため、医師に相談することが大切です
看護師が現場でよく見る“あるある”シーン
- ゴロゴロ音がする → 鼻の奥に鼻水が溜まっていた
- 喉の奥が鳴ってる → 唾液がたまっていただけだった
- ゴロゴロ音が続く → 子どもがブクブク音を楽しんでいた(笑)
- 家族が毎回吸引 → 実は無反応で、痰がなかった
このように、音の原因はさまざまで、吸引しても改善しないケースは意外と多いのです。
不安なときはどうする?家族・支援者の立場から
見極めが難しいときは、一人で判断しようとせず、誰かに相談することがとても大切です。
できる工夫
- 日頃から「この音はいつもの音」と記録しておく
- 吸引前後の様子を動画やメモで残す
- 訪問看護師や主治医に定期的に相談
家族の視点、保育者・教員の視点、医療職の視点。 それぞれの観察と情報を組み合わせることで、より安心・安全なケアにつながります。
まとめ
- ゴロゴロ音がしても、それが“痰”とは限らない
- 状態観察と音の性質の見極めが重要
- 無理な吸引より、“様子を見る判断”も大事
- 体位変換などの対処法も有効
- SpO2が低下するようなら、医師へ相談を
- 不安なときは、ためらわずに相談・共有を!
👉 吸引が必要かどうか、もっと詳しく知りたい方は ➡️ 吸引の判断に迷った時、どうする?【看護師が教える3つのチェックポイント】
この記事が、日々ケアに関わるすべての方の「安心」につながりますように。

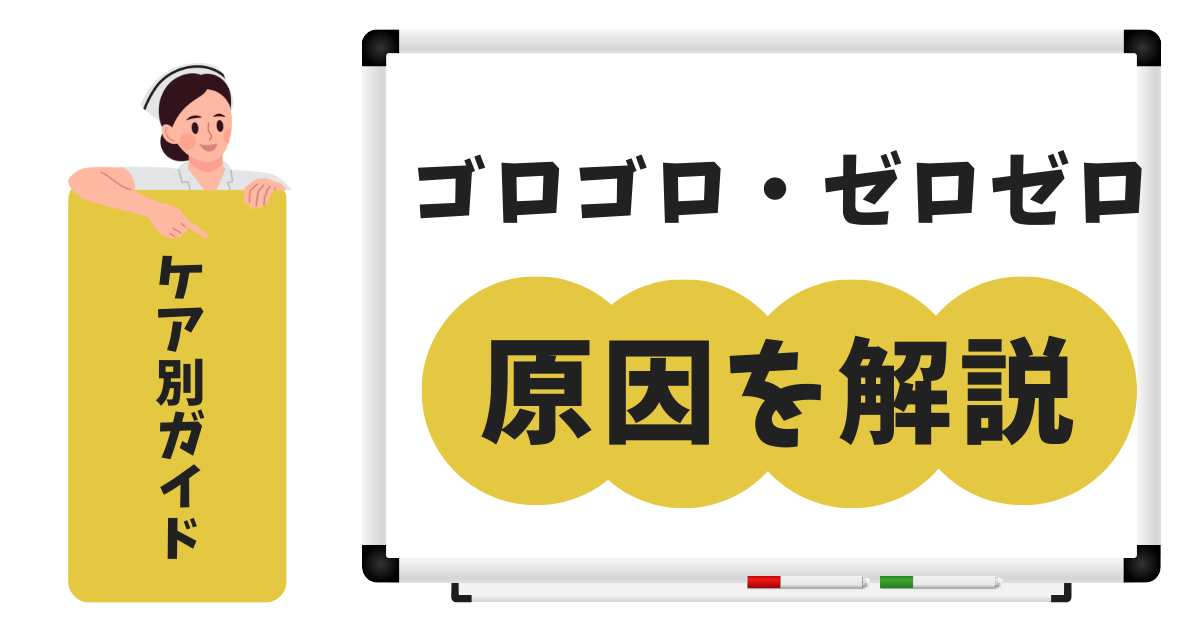


コメント