「吸引って…今、やったほうがいい?それとも様子を見ても大丈夫?」 こんなふうに迷ったこと、ありませんか?
私は看護師歴30年、医療的ケア児・者への支援歴15年の「みつば」です。 高齢者デイサービス、重症心身障害児者施設・訪問看護・学校看護師・小児外来など、多様な現場で吸引のケアを行ってきました。 吸引は、命を守るための重要な医療的ケアのひとつです。 でも実際の現場では、「本当に今やるべき?」「もう少し様子を見てもいいのでは?」と迷う場面も多くあります。 特に、本人が言葉で「苦しい」と訴えられない場合、その判断はさらに難しくなります。
この記事では、そんな迷いを減らすために——
- 吸引を検討すべき【3つのサイン】
- 吸引を急がなくてもよいケース
- 現場で役立つ判断フローチャート
- 経験から得た「判断のコツ」
を、症例エピソードと生理学的な背景も交えて、わかりやすく解説します。
【チェックリスト】吸引を検討すべき3つのサイン
吸引の必要性は、「痰が見えるかどうか」だけでは判断できません。 現場で大切にしているのは、呼吸音・呼吸状態・顔色の3つを組み合わせて観察することです。
① 呼吸音の変化(ゴロゴロ・ガラガラ)
呼吸音は、痰の位置や量を知る重要なヒントです。
ゴロゴロ・ガラガラ音が大きい場合 → 痰が上気道や中間部にあり、空気の通り道で振動している音です。吸引で改善できる可能性が高いです。
音が急に小さくなった場合 → 要注意。痰が気管や肺の奥に落ちて、呼吸の邪魔をしている可能性があります。 → このときは体位ドレナージ(体を横向きやうつ伏せにして重力で痰を移動させる)を試すのも効果的です。
【生理学的ポイント】 呼吸音は、痰の量だけでなく粘稠度(水分量)や気道の狭窄度(細さや形)にも影響されます。乾燥や発熱で痰が硬くなると、気管支などにへばりついて音が変化しにくくなります。
② 呼吸パターンの変化
- 呼吸が浅く速い(成人で1分間に25回以上、小児で40回以上)
- 息を吸うときに肩や首の筋肉を使っている(努力呼吸)
- 呼吸のリズムが乱れている
【症例エピソード】 特別支援学校で支援していた男の子は、普段は穏やかに呼吸していましたが、授業中に肩を上下させる呼吸を始めました。観察すると、わずかなゴロゴロ音と顔色がなんとなく白っぽい。吸引後、すぐに落ち着き、顔色も改善しました。
③ 顔色や皮膚の変化
- 唇や爪が紫色(チアノーゼ)
- 顔が急に赤くなる
- 青白い顔色になる これらは、血中酸素が低下しているサインです。即対応が必要です。
【番外編】SpO₂モニターを活用しよう
SpO₂モニター(パルスオキシメーター)がある場合は、迷った時の判断材料として計測してみましょう。
普段の安定した値よりも低下している場合、痰などで気道が狭くなっている可能性が高くなります。特に、ゴロゴロ音が聞こえないけれど、なんとなく呼吸が苦しそうな時など、判断に迷う時に非常に役立ちます。ただし、機器のアラームが鳴っても、体動や測定部位の血行不良などで数値が一時的に下がることがあるため、すぐに慌てず、数回測り直して確認することも大切です。
逆に、吸引を急がなくても大丈夫なケース
「吸わない」という判断も、現場では重要です。 やみくもな吸引は、気道粘膜を傷つけ、炎症や痰の増加を招くことがあります。
吸引を急がなくてもよい判断基準
- 咳やくしゃみで自力排痰できている
- 呼吸音が徐々にきれいになってきた
- 呼吸が落ち着いていて苦しそうでない
- 痰がごく少量で、自然に飲み込めている
吸引以外のケアも有効
- 水分補給(痰を柔らかくする)
- 部屋の加湿
- 軽く体位を変えて、痰の移動を促す
これで迷わない!吸引判断の現場フローチャート
- 呼吸に伴う音を確認(ゴロゴロ・ガラガラ・ヒューヒュー)
- 呼吸状態を観察(回数・努力呼吸の有無)
- 顔色と表情をチェック
- 必要なら体位変換や加湿などを実施
- 状態が改善しなければ吸引
- 実施後、記録と経過観察
症例から学ぶ判断のコツ
症例1:吸引を急がず観察したケース
デイサービス利用中の高齢女性。昼食後に軽いゴロゴロ音。顔色は良好で会話も可能。水分補給しながら、しばらく座位で過ごし30分後に音が消失。吸引不要で済んだ。
症例2:迷わず吸引したケース
重症心身障害児。体を横向きに変えた後、急に呼吸が浅くなり、顔色が青白くなった。体を動かしたことで奥にたまっていた痰が動き、大量の痰が吸引できた。数分で呼吸改善。即対応が奏功。
まとめ|見て、考えて、動く
吸引は「必要なときに、必要なだけ」が原則です。 観察 → 判断 → 実施 → 記録、この流れを守ることが安全につながります。
【ポイント】
- 迷ったらまず観察
- サインがそろったらすぐ吸引
- 改善がなければ次の手を打つ
👉 次は【吸引を嫌がる子にどうする?信頼を築く3つの工夫】へどうぞ。
執筆者:みつば 看護師歴30年/医療的ケア歴15年 急性期病棟(消化器外科・乳腺外科ほか)、行政訪問指導(700件以上)、高齢者・障害児施設、訪問看護、学校看護、小児外来など幅広く経験。

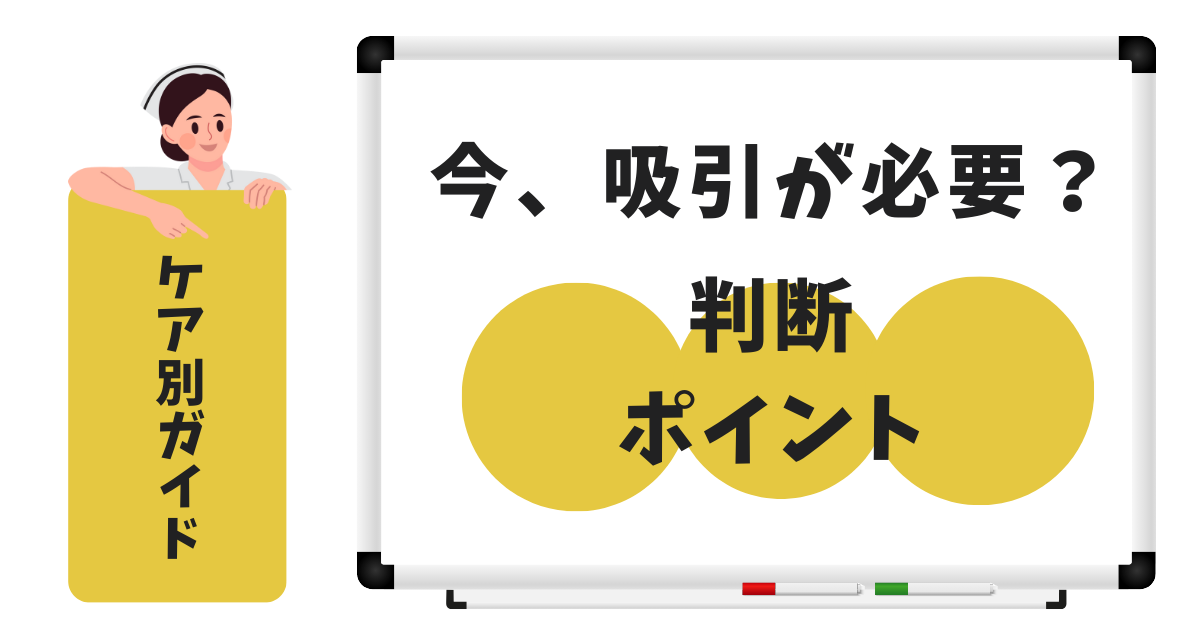
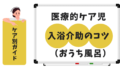

コメント